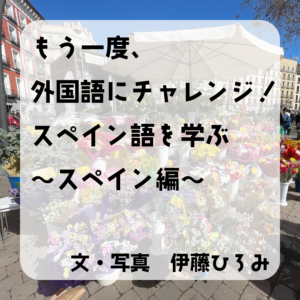第7回 歴史的建造物が語るスペイン・トレドの歴史
文・写真 伊藤ひろみ
外国語学習に年齢制限はない!――そう意気込んで、国内でスペイン語学習に挑戦したものの、思うように前進しない日々が続いていた。そんな停滞に歯止めをかけるべく、現地で学んでみようとメキシコ・グアナフアトへと向かったのが2023年2月。約1か月間、ホームステイをしながら、スペイン語講座に通った(くわしくは、「もう一度、外国語にチャレンジ! スペイン語を学ぶ ~メキシコ編~」をご参照ください)。
1年後、再び短期留学を決意する。目指したのはスペインの古都トレドである。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
<第7回> 歴史的建造物が語るスペイン・トレドの歴史
トレドは人口8万5千人ほどの町である。そんな小さな町に世界中から観光客が押し寄せる。私が滞在中のスペイン人宅からすぐの場所には大きな駐車場があるのだが、そこでは連日何台もの観光バスの姿を目にする。マドリッドからは車で約1時間の距離だからか、首都からやってくる観光客が大半のようである。
彼らが目指す場所はどこか。彼らは何を知りたがっているのか。今回はトレドの観光名所を訪ねながら、その歴史に迫ってみたい。
イスラム教文化×キリスト教文化が生んだムデハル様式
まずはトレド人たちのお勧めの場所のひとつ、セファルディ博物館(Museo Sefardi)を見学する。到着したのは午前10時過ぎだったが、日曜日とあってすでに観光客が長い列を作っていた。入口で手荷物などのセキュリティチェックを受けたあと、建物内へと進む。

細かく手の込んだ内部装飾が魅力の博物館。かつてはユダヤ人たちの祈りの場
壁面装飾が実に美しい。近づいてよく見ると、細かい幾何学模様が施されていることがわかる。上部には、多葉形のアーチが取り囲み、そのいくつかから陽の光が差し込んでいる。寄木造りの天井も落ち着いた雰囲気を醸し出している。それぞれの装飾は手が込んでいるものの、全体としては控え目。白、アイボリー、ベージュ、茶色と色使いもシンプルである。四方を取り囲んだアーチ状の窓の上には、ヘブライ語が刻まれている。2階には、ユダヤ教に関する資料などが展示されている。
もともとここは、カスティージャ王・ペドロ1世の命で建てられたユダヤ教の教会(シナゴーグ)だった。ムデハル様式と呼ばれる、イスラム教文化とキリスト教文化が融合して作り出された建築様式を持つ。14世紀ごろのトレドには、1万人ほどのユダヤ人が暮らしていたという。ガイドブックなどには、セファルディ博物館という名のほかに、トランシト教会(Sinagoga del Tránsito)という名称でも紹介されている。

2階にはユダヤ文化を彩る資料が並んでいる
かつてのシナゴーグに見る究極の美
もうひとつ、ユダヤ教関連の重要な場所を訪ねてみたい。セファルディ博物館からレジェス・カトリコス通りを北へ徒歩1~2分ほどのところにあるサンタ・マリア・ラ・ブランカ教会(Sinagoga de Santa Maria la Blanca)である。
馬蹄形の白いアーチが連なり、圧巻の造り!
アーチは4列に平行に並び、礼拝堂の身廊を5つに分けている。各アーチは八角形の柱で支えられ、柱頭には渦巻模様をモチーフにした装飾が施されている。アーチの上には、花や唐草、星の模様などが描かれている。さらに上部には、セファルディ博物館と同様、多葉形のアーチ、寄木造りの天井という構造。それら独特のデザインと装飾に向けて、床からライトアップするという演出も見事である。まるで異世界へ飛び込んだような気分になれる場所。まさに息をのむ美しさ!

圧倒的な存在感を示すアーチの列。ここでも異なる宗教の混在に出会う
かつてはここもシナゴーグ。その歴史はセファルディ博物館よりさらに古い。1180年、ユダヤ人のための礼拝堂として建てられたが、15世紀初頭、キリスト教の教会へと改築された。現在、正面上部の壁面には、十字架が掲げられているのが見える。ユダヤ教会からキリスト教会へ。トレドの歴史とともに歩んできた文化遺産である。

壁面、天井などもこだわりが感じられる造り
カトリック教会のミサに加わって
レジェス・カトリコス通りをさらに北へ進む。左手に見えてきたのが、サン・フアン・デ・ロス・レジェス教会(Monasterio de San Juan de Los Reyes)。デコラティブな外観や内装など、典型的なカトリック教会の佇まいである。ちょうどミサが始まる時間に着いたこともあり、そのまま席について、信者たちとともに祈りの時間を過ごすことにした。
礼拝堂内は広く、大勢の人が集っている。カメラを置いて、彼らの様子を見たり、いっしょにお祈りしたり。もちろんミサはスペイン語で行われるため、正確な言葉の理解には遠く及ばなかったが。

豪華な中央祭壇。ミサの時間には多くの信者で賑わう
ここは、イサベル女王とフェルナンド2世が1476年に「トロの戦い」でポルトガルに勝利したことを記念して創建された。聖堂と修道院があり、ムデハル様式とゴシック様式が混在したスペイン独自のイザベル様式となっている。

技巧的なアーチが連なるサン・フアン・デ・ロス・レジェス教会内の回廊
これら3つの教会は、いずれもトレド旧市街の北西に位置し、付近のエリアは、ユダヤ人居住区として知られている。なぜトレドにユダヤ人が住んでいたのか、過去には彼らの祈りの場が作られたのか。それらを知る手がかりとして、スペイン、トレドの歴史を遡ってみよう。
異文化が混淆する町、トレドの魅力にふれて
紀元前1000年ごろ、イベリア半島に最初にやってきたのがフェニキア人だと言われている。その後、ローマによって征服されたあと、トレドは6世紀に西ゴート王国の首都となる。さらに711年から約400年間、スペイン南部からやってきたイスラム教徒の支配下となるが、その間もトレドにはキリスト教徒、ユダヤ教徒らが共存する社会を形成していた。だが、状況が一変したのは1492年。キリスト教徒の支配により、イスラム教徒、ユダヤ教徒が追放されてしまう。
トレドには、セファルディ博物館やサンタ・マリア・ラ・ブランカ教会など、過去にイスラム教徒、ユダヤ教徒も暮らしていたことを示す建築物が随所にある。それはこの町の懐の深さなのか。異なる宗教でありながらも、それぞれの信者がこの町に共に暮らしていたという事実に驚かされる。さらに、長い歴史の中で支配、被支配が大きく変化し、住民の暮らしだけでなく、町の景観にも大きな影響を与えた。彼らが残したものが、今や世界の遺産として高く評価され、トレドの魅力をいっそう奥深いものにしているのである。

ユダヤ人地区は行き来する人も少なく静かなエリア。足元にはこの地区を示すマークが埋め込まれている(左下)
[ライタープロフィール]
伊藤ひろみ
ライター・編集者。出版社での編集者勤務を経てフリーに。航空会社の機内誌、フリーペーパーなどに紀行文やエッセイを寄稿。主な著書に『マルタ 地中海楽園ガイド』(彩流社)、『釜山 今と昔を歩く旅』(新幹社)などがある。日本旅行作家協会会員。