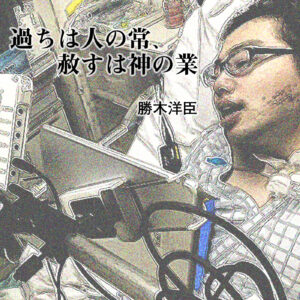無名作家の日記――菊池寛氏の作品よりタイトルを仮借
俺は売文屋、もとい作家である。俺が作家であることの理由は単純明快である。他にできることが何もないからだ。クラウドコンピューティングがどうしたこうしたというオシャレな世界からは早々に病気で脱落し、作家という境涯に身を沈めることになった。AI時代の文学が云々されることもあるが、作家は古代からあるような古色蒼然たる職業で、やっていることも万古不易でほとんど変わらない(と思う)。考えてアイデアを出して、そのアイデアを表現するところの文章を書くだけである。
共同して作品を創り上げる、すなわちコラボする機会なんてあるはずがない(たとえリレー方式の作品であっても、担当したところは責任を持って一人で書くのである)。一人で考え、一人で書き、作品の出来不出来のツケを一人で払う孤独な行である。このように孤的な作業であり最近の社会の趨勢を容易に寄せ付けないことが、作家という職業を保守的なものにならしめているのであろうか。よく分からないが。結局現代社会から俺の被っている恩恵など、今の世の中パソコンというものができていて、麻痺でろくにペンが握れなくとも文字を入力できることだけである。
昔、司法試験の夢潰えて何のために書いたものであるかよく分からない入院中の記録を偉い先生にお見せしたら、その先生はいたく俺を嘆賞して「文筆家としてこの世に影響を与えることができる……」とおっしゃった。うれしいことはうれしかったが、俺には一種の妥協であるように見えた。率直に思ったのは傍白〈ハア。もはや法律家としてマトモに生きられないことが確定したから作家であきらめろ、ということですね〉だった。バリアフリーだユニバーサルうんちゃらだと云々されることがあるが、結局障害者というのは社会の表舞台に立てず、みんなに遠慮しながら、アウトローな生き方をしなくてはいけないということである。折角それなりに頑張ってそれなりに偏差値が高い学校を出て、オリンピックの規定演技をこなすように人生をやり過ごしていたのに、病気という一事ですべてが台無しになり、それまでやってきたことは何にも意味がなくなってしまった。
作家一本でやっていくのと法律家とどちらが偉いだろうか。決まっている。疑いようもなく作家ではなく法律家である。法律家というのは難しい交渉もこなせなければならず、酒の席では顧客との間でエスプリの効いた会話が楽しめ、それでいて情報収集は怠らず……というように手垢の付いたような言い方を許させてもらうなら「総合力」、「人間力」が求められる。文章を作成する能力など「人間力」として要求される数ある能力の内の一つに過ぎない。俺のような障害者でも何とか「作家」の末席を汚していられるのも作家という職業が取りあえず文章を作成する能力があれば足り、「人間力」がそんなに、というかほとんど要求されないからである。
文章を作成する能力に限って見てもその能力は作家の独擅場ではない。文章作成能力というのは取りも直さず「お勉強のできる」能力である。これこそ法律家が他の追随を許さない能力である。作家のプロフィールを見ると、少なくない割合が文学部ではなく法学部出身者である。法学部の方が文学部よりも偏差値が高い。文学部ならではの法学部学生が教えてもらえないことがあるのかもしれないが、小説を書くということに限って見れば、お勉強さえ出来るのならば教えてもらえないことがあっても構わないのである。
人間観察をして人間というものを見抜くことが大切だと言われることがある。理系はいざ知らず、文系の分野なら間違いなく要求される能力である。この能力についてはどうか。法学部と文学部全体的な傾向は知らないけれど、自分の所属していた大学は面白い人間が多数おり、人間観察の格好の対象であった。だからしょっちゅう俺は人間を観察させてもらい、結果として人間を見抜く能力も並の人間にひけをとらない位涵養されたと思う。学生時代を思い返すと、いっつも大講義室の真ん前に陣取り、講義後先生と暫時俺には意味不明なレヴェルの高い会話にうち興じる学生やら、ゼミで俺が訥々と発表した後ものすごーく鋭く俺の発表の欠陥を指摘して俺をたじたじとさせて何も言えなくさせた学生がいたことを思い出す。そういう怪物・化物が身近にいたことに比べれば、自分が今身を置いている環境は本当にラクである。本を読んでいると時折ハッとして文章から目を上げることがある。学生時代、自分の周りにいた化物のごとき奇人・変人たる彼らはどこへ行ってしまったのだろう、と。もう二度と相まみえることはないに違いない、と思う。一抹の寂しさを覚える。今はプレッシャーもストレスもないが、どことなく物足りなくつまらない感じである。
家にじいっといてもネットニュースでは「〇〇賞を受賞した△△さん……」という報が流れることがある。こんな時俺はフッと冷笑を漏らす。俺はその△△さんがどこの大学を出ているのかネット検索で調べることを習わしにしている。どれどれ……ああ、早稲田の文学部出身ですか。世間的には早稲田でもかなり頭がいいとされていることは重松清『とんび』の口吻からも窺えるが、全然大したことがない。俺の場合もし自分の子が早稲田の文学部に行くと言い出したら、大変なショックを受けて二、三日起き上がれないと思う。
読書でもこのような態度は反映されている。俺は小説でも外国の小説、しかも時代錯誤的なシェイクスピアやゲーテ、ジェーン・オースティンやムージルといった古ーいものばっかりを読む。俺が古風な性質だからなのが一番の理由だが、他にも理由はあってそれは自分が現代の日本の作家から遠い所に身を置くことによって、彼らを見下したような態度がとれるからだ。表向きには「過去の知的遺産は汲めども尽きせぬ泉のようなもので、源泉(=古典作品)を押さえさえすれば支流である現代のトレンドに振り回されることはない」などともっともらしいことを言っているが、本当は古い時代の外国の本を読んでいると、遊んではおらず額に汗して働いているかのようにハタからは見えるし、あえて現代の日本の小説家から距離をとることで現代の流行には振り回されず超然とした態度をとることができるのだ。不思議なもので、学生時代は自分が法律家になることを寸毫も疑っていなかったので全く小説家というものに無関心でいることができ、気楽に現代の日本の小説家の作品に親しむことができた。村上春樹氏の作品は手に取ったし、池井戸潤氏の『半沢直樹』は笑って観た。でも病気に罹って司法試験がダメになって退院した後の2020年に続編の『半沢直樹2』が封切られた時、俺はドラマを一秒も観なかった。今を時めく作家という存在に心を惑乱させられたくなかったからである。「隣の花は赤い」とは含蓄のあることわざである。まさに我々は近くの花を赤いと思うのであって遠くの花には無関心でいることができる。こんな現代の作品について勉強しない怠惰な態度だから、新人賞もなかなか獲れなくてデビューするのに大いに苦労した。でも自己の精神の安定のため、それでもいいと思っている。
ここまで語って、俺がいかに性格が悪いのか露見したと思う。要するに俺は今は物足りなくてつまらないが太平楽な気分でいるのだ。俺は病気になったことで東大法学部出身者のラットレースから脱落して、人と比較して余計に苦しめられることがなくなり、一方作家の中では俺が一番頭がよいナンバーワンだと得意な気分だったのだ。
しかし、こんな能天気な暮らしは長くは続かなかった。自分の本をお情けで出させてもらっている文学雑誌をめくったら、見覚えのある男の名前が目に飛び込んできた。「万城目幸太郎」という名前が。俺は驚いて、ネットで検索をかけた。学問の道に進んだことは大学の卒業式(大学院ではなく大学である。)の総代スピーチでそいつが首席で総代に選ばれてスピーチをしたので知っていたがそいつのことは大嫌いだったので、卒業以来彼の道行きについては1ミリも調べてこなかった。東京大学法学部を出て助手に収まって以降、法学政治学研究科の大学院生と教職員とが使う図書館での立ち聞き(まだこの頃は俺は障害を負っていなかった。)によると、彼は無事助手論文を書き上げた後ドイツに在外研究もして論文をたくさんたくさん書いて、助手⇒講師⇒准教授という順調なキャリアを築いてきたようだ。まさか小説家として彼がデビューしたなんて。
慌てたが、すぐに思いなおした。待て待て、あんな他者の痛みにも共感できないような酷薄な人間にロクな小説を書ける訳がない。それに俺が何とかデビューできたのも学歴が無駄に良くて、なのに普通の人は絶対にならないような稀な病気に罹ったという経歴がレアで、出版社が宣伝しやすかったからだろうから、どうせ俺と同学出身のこの男が作家デビューしやすいよう弾みをつけるために選考過程でひいきされたに違いない。読んで、作品の欠陥を指摘してやる!
……読んでみた。ドイツへ在外研究に行った田辺という男性がアンナという女性と恋に落ちるというもので、話の大枠は森鷗外『舞姫』をパクっていることは明らかだった。『舞姫』が執筆された当時のドイツ社会と現代のドイツ社会とどう違うのかなどが文学研究者の学究の対象になろう。でもそんなことよりも何よりもこんな作品、ドイツに滞在したことがある人でなければ書けない名作である。たしかにドイツに行ってアバンチュールを楽しんできたというのは嘘の作り話であろう。万城目は在外研究の際家人を伴ったに決まっており、火遊びなんかする訳がない。森鷗外も当然妻子を伴ってドイツへ行ったのであり、女遊びなんかしなかっただろう(いや、遊んだのかもしれないが、せいぜいで行きずりの相手がいただけで少なくとも昵懇の恋人はいなかったに違いない)。ただそれ以外の描写はおそらく実体験に裏打ちされており、活き活きとしている。夜の暗い闇が朝方の燦燦たる陽光にかき消されるさま、夜が明けて人々があいさつを交わし、市を開く準備をするガヤガヤとした喧噪、教会の尖塔や壁が昇ってくる日の光を受けてキラキラと輝く様子、カリーヴルストを屋台で注文して出来上がりを待っている間に辺りに漂う香ばしい香り、カリーヴルストを頬張り上機嫌にアンナと連れ立って歩く田辺……俺の作品は本当にスケールが小さく、テーマが家庭における夫婦のいざこざやら小学校における生徒同士の人間関係やらそういうせせっこましい世界を扱っている。障害者がどのように遠出しろと言うのだ。日本より治安の悪い外国で車いすを操作していたら俺に目を付けたごろつきたちが俺を取り囲んでボコボコに折檻して所持金もパスポートも奪って車いすを俺から遠くへやってトンズラしていくだろう。それで、満身創痍の俺は命からがら領事館に助けを求めたくとも車いすを遠くにやられてできず、往来で「ヘルプミー、ヘルプミー」とフガフガ叫ぶことしかできないであろう。そして通行人は障害者の俺と関わり合いになることを恐れて完全無視して通り過ぎるであろう。
小説というのは人間の心理を描くもので、そこを押さえれば何を題材にしていようと構わないと俺はうそぶいてはいるが、単に異国情緒を味わわせ、外国の文物に憧れを抱かせることも(特にインターネットがなくグローバリゼーションが進んでいなかった旧時代においては)文学の大きな役割の一つなのである。だから紀行文というジャンルがあるのである。国内旅行ならまだしも海外旅行の紀行文なんてろくに外出することができない俺には絶対手出しのできない分野である。結局俺のような障害者の売文屋……ではない作家は、小さな日本の小さな東京の安普請の家で、日本語を生産し続けねばならないのである。
あくる日、俺は自ら電動車いすを操作して、編集者と新しい小説について話し合うというかこっちはろくにしゃべれないから一方的にあちらの意見を聞くため日本橋に赴いた。コロナ禍をきっかけに最近オンライン会議が普及してきたから、全部オンラインで済ませてもよいのではないかとも思うのだが、編集者さんの朱筆が入った原稿を受けとって(これもWordの機能で電子的にやり取りできないことはないが。)話を聞く必要があるというのが社の方針らしい。これはまだ分かるが、本当の理由は全くもって意味が分からない。何でも直接会うことで、お互いの体から発している微弱な電気信号を受信し合い、互いの絆を深めていく……らしい。こんな令和の時代にそぐわないようなオカルティックな理由にも基づいて出社しなければならないのである。
電動車いすでの移動は思いのほか骨が折れる。電車に乗るのはまだよい。駅で障害者手帳を見せてあとは駅員さんに任せて電車に乗りこみ(交通機関の中でも日本の電車は、特にJRは洗練されていると思う。外国の電車は……推して知るべしだろう)、あとは周りの乗客から白い目で見られ、視線から生じる圧迫感に耐えていれば、近くの手すりにつかまっているだけで、目的の駅まで行く。もう白眼視されることにも慣れた。もしジロジロ見てきたら、こっちもジロジロ見返してせいぜい人間観察させてもらう。幸いなことに出版社までは電車一本でいけるのだから、乗り換える必要はない。因みに乗り換えがあったとしても駅員同士で連絡を取り合っているからホームのどこで待てばいいかまごつくこともない。
問題なのは駅の外の道である。やはり徒歩と異なり小回りが利かないから移動のためには広い場所と道とが必要であるし、健常者は通行する際もっと俺から距離をとってほしいと思う。顔面等が衝突しそうだからみんな気遣ってよけてほしいと思うのだが、道行く人は猛然と車いす上の自分に向かってきて、ぶつかるかという寸前でほんの少し身をひねらせてスレスレでよけるのであり危なっかしくてしょうがない。そこで自分は充分距離がある間に「スイマセーン、スイマセーン」と声を挙げ、今から車いすが通るアピールをしているが、フガフガで本当に気づかないだけなのか気づいていても障害者と関わり合いになるのを恐れて気付かないフリをしているのか、みんな完全無視で大層危ない。
出版社ビルになんとか入れた。でも入った後も会社のデスクがひしめき合い、資料が雑然と積み上がり、通行の邪魔をする。あと健常者には何気ないパソコンの電気コードやらゲラ刷りの紙切れやらを車いすの車輪が巻き込みそうである。会社は我が家よりも片付いているのだが、勝手知ったる我が家だし、我が家だと大きな移動を強いられないから、我が家の方がストレスが圧倒的に少ない。悪戦苦闘していると、程なくして、見慣れない男性(見慣れなかったのは卒業以来十年以上経ち、相手の顔が変わったからである。)が「こんにちは」といって入ってきた。あ、この鼻につくイヤな感じの声は。
もったいぶった感じで自己紹介を始めた。何でも自己紹介の内容によると、東京大学法学部の教員資格で、研究者として順調にキャリアを積んできたがこの度たまさか自分の文章が新人賞を獲れたので、研究者との二足のわらじで、あくまで研究の「余技」として小説を書いていきたいと言う。この時俺は遥か昔の大学教授を思いだしていた。その人は国際関係論がご専門だが、ロマンスグレーで英語ペラペラな帰国子女で、研究の片手間に映画評論を行っているという専らの評判だった(いや、映画評論の片手間に研究をしていたのだろうか)。今時流行りのあまり一つの職業にこだわらないというオシャレな生き方だ。しゃべれもせずノロノロとパソコンで文字を入力していくことしかできない俺には真似できない芸当だ。俺は反射的にふざけやがって!と思った。傍白〈こちとら副業感覚でお遊びで小説を書こうっていうんじゃないんだ!文字を刻んでいくことしかできないから、小説に全力投球するしかないんだ!〉
彼と目が合った。俺の顔も歳月と病魔とによってずいぶん変わってしまったのであり、大体俺は障害を負って普通の人でなく車いすの姿になってしまったのであり、俺の正体に向こうは気づいていないのかもしれない。それを期待してジロジロとそいつの顔を見ていたら向こうは俺の風体のどこかに面影があったのか気づいたようで、目が合ってうぐぐぐ……とお互い気まずい雰囲気になった後何も言わず黙礼した。にもかかわらずスピーチの後出版社の人が
「万城目君と駒形君は同窓で同年に入学だよねえ。もしかして知り合いなんじゃないの~?」
と言った。万城目幸太郎はクイと眼鏡の縁を上げて、
「へえ。同窓の方ですか。全く知りません。初めまして。お初にお目にかかります……」
とわざとらしく自己紹介をし、大学の教職員が使う名刺を差し出してきた。俺も昔大学の購買部で名刺を作ったが当時は元気だったので、かつては健康だった自分を思いだし気分が悪くなった。その時は渋々名刺を受け取ったが、一応連絡先はスマホに登録した上で、名刺はムチャクチャに破って、健常者用のトイレのゴミ箱に叩きこんでやった。もしかしたらビリビリになった名刺の残骸を目にして、彼は少なからず衝撃を受けるかもしれない。ざまあみろ。
こう彼に対する敵愾心が剥き出しでは俺はそいつに執着している、仲良くしたがっているのにつれなくされているから一方的に彼を憎むいわゆるツンデレだと思われるかもしれない。断じて違う。それが証拠に卒業以来彼の名前をネット検索したことがない。
間もなく奴の処女作は出版された。本の帯には麗々しく宣伝文句が書いてあって、「東大の若き俊英の鮮烈なデビュー!」と記されていた(蛇足だが三十代って若いのか?たしかに研究者の世界では若いが。)。売れ行きは好調で本が書店で平積みされ、重版がかかった。比較的硬質な純文学のジャンルなのに十五万部売れたらしい。俺は小説でも映画でもNetflixでも、内容がどれだけ道徳的で美しくても作者にロイヤリティーがどれだけ入ったか計算してしまう。えー新人賞の作品だから、印税を受け取っているとしたら、それは重版がかかった分だけ。で、この小説は純文学のジャンルなのだから、マイナーで普通はそんなにたくさん出版はしない。出版業界では純文学の書籍で一万部売れれば成功である。印税の率はわが社の規程では一冊当たり、定価の8%である。だから万城目に入った印税収入は書籍の値段×重版以降の売れた部数×印税の率=1500円×(15万部-1万部)×8%=1680万円だ。結構な額だ。しかも映画化なんかされれば著作権収入が入ってくる。二足のわらじでダブル・インカムと誇ってよい。金金金とうるさいかもしれないが、安定した収入を文筆業で得られるかどうかということは作家として一人前かどうかを測る重要な指標なのである。一応俺は騙し騙し作家のようなことをやっていられるが、専業作家でダブル・インカムなど望むべくもないのでカツカツの暮らしだ。こんなぽっと出の人間が脚光を浴びるなんて!
それから間もなくして、俺は彼が第二作を精力的に書いていることを知った。俺はそんなひょいひょいと小説を書いていくことなどできない。ゲームコントローラーで、慎重に一文字一文字入力していくしかない。健常者の作家さんなら一日六千文字は書けるらしい。俺はどんなに死力を尽くしたとしても書ける量はその三分の一だ。出版社の人も明らかに俺よりも万城目を持ち上げるようになっていた。「万城目『先生~』」とかいって。当たり前だろう。出版社は一営利企業に過ぎず、ボランティア団体ではない。10本指がパーと動き多作で生産性の高い万城目を重く用いるに決まっている。作家自体はものを教える仕事でもないので、「先生」と呼ぶことはいかがなものかと個人的には思っているが、わざわざ「『先生』ではない!」と青筋を立てて怒ることも何かしょっている感じでしたくないし、俺がデビューしたばかりの時「先生」と持ち上げられることはそれまで仕事に就いたことのない俺にとってはいきなりのことで衝撃的で、やはり気持ちの良い天にも昇る心地だった。よって今後も、作家を気持ちよくさせて、やる気を出させるために「先生~」と呼ぶ悪しき慣行は継続するだろう……とここまで考えたが、彼は東京大学の准教授でものを教える仕事に就いているのだから、「先生」と呼ばれても全くおかしくはない。ただ「先生」と呼ばれ続けると彼の傲慢な気質が助長されると思う。
別の日、俺が今制作中の作品のこれからの展開について編集員の中野君から意見を聞くため出版社まで出向いた。そこで、嫌な会話を聞いてしまった。「万城目」というワードに反応して耳をそば立ててしまったのが命取りであった。
「ねえねえ万城目先生ったらすごいのよ。もう来月には出稿して印刷機回るところなのよ!」
「僕も一社員としてではなく、一読者として先生の小説が楽しみで。カザフの空気感が味わえないかな。カザフなんて行ったことないから」
「大学の先生、駐在員、現地邦人、来日した村の出身者から綿密に聞き取りしていて現地取材もしているから完璧ね!」
カザフに荒涼と広がる大地にポツンと佇む車いす姿の自分を思い浮かべ、かぶりを振った。無理だ。俺には書けない。それにしてもカザフなんて単語を聞いたのは十数年ぶりだ。たしか経済産業省の説明会でカザフに原発を輸出する云々という話で聞いたワードだ。この時、俺は経産省の説明会に出ていた往時の自分を思いだしていた。かつての溌剌とした自分、健康だった自分、髪が豊かだった自分、若かった自分、リクルートスーツに身を包んで、革靴で地面を鳴らして往来を闊歩していた自分……俺はいたたまれず、そそくさとその場を去った。
中野君からは話が上手く聞けなかった。上の空だった。こうやって話を聞いたら、たとえメモを残していたとも、すぐ作品を書かなければ訳が分からなくなってしまう。録音を残しておくんだった。それまでは人の話はよく聞いている方だったのでボイスレコーダーを用意することがなかったので完全に油断していた。メモの字はぐちゃぐちゃで、見るだけで吐き気を催すので、しまいには見なくなった。
数日経過。編集員の中野君がインターホンを押す。しばらく経つが、誰も出ない。
「先生、いらっしゃるのは分かっているんですよ。外出用のリフトの床が上がったままなので、居留守を使われているということですよね?」
ピンポン、ピンポン、ピンポーン♪
耐えられなくて、
「ウルサーイ!それにインターホンもタダじゃねえんだ!電気代がかかるだろ!」
「やっぱり居留守だと思ったからインターホンを何回も押させてもらいましたよ。先生はケチなので(笑)。上がってもいいですか?開いていますか?(「ハイ」と返事)じゃあ失礼します」
ギイ、バタン。中野君が俺のベッド脇でしゃがむ。
「先生、折角会議で雑誌のスペースを獲得したのに、3日経過しても何の音沙汰もないなんて!原稿はどのくらい出来上がっています?このご様子ではまだ一文字も書かれていないようですね。即刻仕事に取り掛かって下さい。先生はただでさえ遅筆なんですから!」
「……中野君、僕はもうダメだよ……」
「えっ?」
長くなるのでパソコンに入力した。
「僕は病気になってホッとしていたんだよ。万城目君のような同窓の思い上がった連中からやっと逃れることができて。あとは小説の世界で小さな座を占めながら心穏やかに暮らしていければいい。そう思って油断していたんだ。
でもそんな中万城目君が来てしまった。知っての通り、法学も文学も文字を刻む世界という点で共通しており、がり勉の人、お勉強のできる人が成功する。どんなに心根が悪い人間でも偏差値さえ高ければ、成功する。その典型例が万城目君だ。彼の実際のパーソナリティーは知らないよ。でも僕が彼と付き合った経験からすると、彼はかなり自己中心的な人間であることは間違いがない。彼は既に法学の分野でひとかどの人物にもかかわらず文学の世界でも一流の成果を出し、成功するなんて。折角僕は文学の世界に身を置こうと考えていたのに、またもや万城目君が邪魔してこようとは!」
ポツリと黙っていた中野君が言った。
「僕は……駒形先生の文章、好きですよ。夏目漱石が芥川龍之介の文章に寄せた感想のような感じです。内容や表現がユーモラスで自然な可笑しみに満ちているけれど、ふざけていなくって……」
自分の文章が好きだというファンレターもほとんど受け取ったことがなく、中野君もほとんど俺の作品の感想を述べたことがないので、意外だった。
「確かに万城目先生は素晴らしい作家です。でも先生は万城目先生には描けない世界を描いている。あなたの文章を待っている人が僕をはじめとして絶対にいるんです。車いすで元気に出社されていた先生に早く戻られて、その人たちのためにも書いて下さい。お願いします(深々と頭を下げる)」
思わず、こちらもお辞儀する。中野君は続ける。
「そうそう、この経験を作品にしませんか?人間嫌なことがあった時はそれをネタに変えるとよくて、作家はそれを商売にできる最高の職業なのです」
中野君が去った後、取り掛からねばならない仕事そっちのけで、今回の経験を基にした話をこういう書き出しで始めた。
「俺は売文屋、もとい作家である……」
(了)
[ライタープロフィール]
勝木洋臣(かつき・ひろおみ)
1989年生まれ。大学時代は東京大学合気道部で汗を流す。2014年3月、東大法科大学院卒業、5月の司法試験を目前に控えていた。大学院在学中、予備試験を21位の好成績で合格していたので司法試験の合格は約束されたも同然だった。そのようななか4月にめまいで大学病院を受診したところ、悪性脳腫瘍が見つかりそのまま入院、手術。しかし翌日から覚醒が悪く、手足も自分の意思では動かなくなり、約1年以上意識が戻らず意思疎通ができなかった。1年過ぎた5月ごろ、目を閉じる合図でのイエスノーの意思表示は出来るようになったが、かすかに動く左手の薬指で、「あかさたなスキャン」という方法で簡単な会話が出来るようになった。だが、膨大な時間がかかった。本格的なリハビリが始まり、その後はパソコンも動かせるようになり、司法試験受験を目指すことも夢ではなくなった。長い闘病生活のため、5年間という期限付きの司法試験を受験できたのはたった2回。1回目の司法試験では、試験監督にパソコンのトラブルを伝えるときのなどに「レッツチャット」は活躍。「レッツチャット」はシンプルさゆえ、故障やトラブルもなく、電池でも動くので外出時にとても便利という。2回目の試験では、あと6点で択一試験に合格できるところまでいった。現在は自宅に戻り、リハビリを続けている。少しずつだが、回復し続けている。そのようななか、短篇小説が執筆され、連載にいたった。