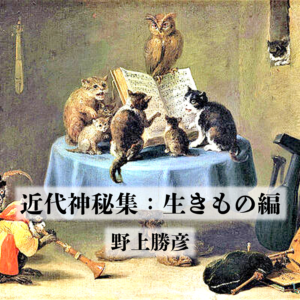狐雨綺譚
プロローグ
わたしは山と里の境にひっそり棲む。
名は捨て、肩書きもない。あるのは、慎ましい誇りといくばくかの知恵、そして少しばかりの化けの技だけだ。
空の底に湿った風が潜り込む。稲の葉がざわつき、野の匂いが変わる。
――狐の嫁入りが近い。
昔、あれもまた、こうして始まった。
1
あの日、空が抜け落ちたような大雨が、神の祟りよろしく地面を叩いていた。
降り出したのは良く晴れた午前の終わり頃だった。にわかに暗くなったかと思ったら、突然、雷が落ちた。里芋の葉を被って茂みのしたで様子を見ていたが、天の怒りは止まなかった。ごうごうと川のように降り注ぐ雨の音。空気はぬるく、どこか焦げ臭い。
里へ向かう畦道(あぜみち)に、小僧がひとりしゃがみ込んでいた。笠もなく、片方のわらじを失くし、泥に膝をついている。歳は十五ほどか。
わたしは杉の陰で姿を人に変えた。色白の若侍の形が、このあたりでは無難だ。
武士らしい声音を使って、呼びかけた。
「いかがした、小僧」
小僧は目を見開き、しばし呆(ほう)けたようにわたしを見上げた。目鼻立ちは並みだ。小刻みに震える肩。空腹か、恐怖か、あるいは両方か。
少し丸顔の小僧が言った。
「おら、奉公先を、飛び出しちまったんです」
――丁稚か。
理由を問えば、主人が悪いのではなかった。主人の女房が気難しく、ものを投げ、理屈なく叱るのだという。
里芋の葉を笠代わりに被せ、裾を直してやった。
「雨宿りくらい、させてやろう」
祠へ案内し、笹で風除けを作る。
丁稚は震えが止まると、雨音の合間に問うた。
「晴なのに急に雨が降ってくると、狐の嫁入りだって、ばっちゃが言ってました。狐って、本当に嫁入りするんですか?」
わたしは小さく頷いた。
「むろん、するとも」
人とは違う嫁入りのことを、少しだけ話してやった。
狐が嫁ぐときは、里に煙が流れ、山に霧が立つ。太鼓は打たれず、酒も注がれず、ただ静かに、枝を折る音だけが遠くで響く。相手もまた狐とは限らぬ。蛇である時も、霊である場合もある。
わたしは呼び水の絵解きをしてやってから、付け足した。
「狐が人に嫁ぐ例だってあるぞ」
丁稚は瞳を輝かせた。
「本当ですか? だったら、きっと今日もどこかで、狐が人の花嫁になってるんですね」
わたしは曖昧に笑った。
「そうかもしれぬ。だが狐の嫁入りは、誰かがいなくなる時でもある」
そのとき、また遠くで雷が鳴った。
夜になると雨はやんだ。ぬかるんだ畦道を、丁稚とともに歩く。
わたしは問うた。
「帰るのか?」
少し間があって、気が落ち着いたように丁稚が頷いた。
「はい。女将さんはこわいけど、旦那様は良くしてくれました。逃げたままじゃ、顔向けできません」
子狐のようにうつむいて、里のほうへ歩くその背を、わたしは黙って見ていた。山の民なら、そこで突き放していただろう。
――どう扱うべきか。
わたしには、もうひとつの顔がある。
「ここで、ちょっと待っておれ。悪いようにはせん」
わたしは丁稚を地蔵の側に残して、里の裏手に回り込み、藁屋を訪ねた。そこに棲む老婆――とされる者がいる。わたしの姉だ。年経た古狐で、人の皮を着て長く里に潜む。
姉は炉端で芋の皮を剥きながら、わたしの話を聞き、目を細めた。
「奉公口に戻すにしても、筋が要るな。――あの女将は口が辛い。だが旦那は義理を重んじる。ならば、狐に誘われ山で迷った筋立てにすりゃ、誰も咎めはせん」
さすが年の功だ。
「じゃあ、あんたがその迷わせた狐をやるんだ」
姉は鼻で笑い、炉端の火を弄(いじ)った。
「まったく、あんたは昔から面倒な拾い物ばかりしてくるね」
わたしは、地蔵まで戻り、丁稚の顔を覗き込みながら言った。
「じゃ、ついて来い」
先に立って、藁屋へと向かった。
その晩、姉は手筈通り、小さな提灯を灯し、丁稚の手を引いて、山道を一度登った。泥濘(ぬかるみ)でわざと転び、足をくじいたふりをした。
翌朝、丁稚は里芋の葉を被って、わたしの付き添いで奉公先に戻った。
「迷子になっていた老婆と出会い、助けようと案内しました」
嘘も方便、というそうだが、この場合などが当てはまるだろう。関係を円滑にし、誰一人、傷つけるものではないからだ。
旦那は安堵し、女将は笹のしおりを渡した。黙った赦しだ。人というものは、言葉でなく、形で赦す場合もある。
その夜、わたしは山に戻る途中、満月を背にした提灯行列を見た。
狐の嫁入りだ。
月の光に煙が混じる。提灯の列が、山の斜面をすうと横切る。音もなく、影だけが流れていく。
あの中に、かつてわたしが想った娘狐がいるかもしれぬ。あるいは、知らぬ顔の誰かが、今夜、嫁ぐのかもしれぬ。
どちらでもよい。
嫁入りとは、何かを捨てて何かを得ることの謂(い)いではないか。人でも、狐でも、それは同じだ。
丁稚は、奉公を選び直した。わたしは、名もなき山の影に戻る。
そうして世界は、今日も正しく、少しだけ騙されている。
2
あれから幾度か雨が降り、里芋の葉も一段と大きくなった。
あるとき、わたしは物好きの心に駆られ、丁稚の様子を見に里に下りた。姉の手を煩わした例だし、女将さんとうまくやって行けているか、多少気になったという事情もある。
丁稚の姿は、畑のそばにあった。用向きの帰りだろう。
脇目も振らずスタスタと歩き、ついに、その後ろ姿は商家の脇戸に吸い込まれた。
裏手へ回ると、土間から若い娘の声が立った。生垣から覗いて吸い込まれた。たすき掛けした女中だった。竈(かまど)のそばで何かを広げている、
――袖口からのぞく手首が、月の光を溶かしたように白い。
その時、娘がふと振り返った。目が合い、笑みがこぼれる。
あれは人の笑みではない――わずかに光を宿す瞳。わたしにはわかる、同じ種の匂いだ。
女中に化けた狐が、里で人として暮らしている。しかも、その視線の先には、丁稚がいる。
加えて、彼女の尻の辺が少し膨れていると見えたのは、わたしの気を引いた。
ふたたび姉に話すと、彼女は口の端を上げた。
「そりゃあ秋口の芽だね。ほっときゃ育つが、霜にやられることもある」
思わせぶりな微笑はなかなか止まなかった。
3
翌春の終わり、里芋の葉が伸び始めるころ。わたしは、また里へ下りてきた。
雨は降っていなかったが、空は曇り、すでに湿気を帯びている。こんな日は――何かが動く。
かつて老いた狸が言っていた。
「狐が来るときは、風が立つ」
だが、風ではなく匂いで分かるのがわたしだ。里の空気に混じる、焦げた米ぬかと、土間の湿り。そこにもう一つ、かすかに香るのは――若い汗と鍬の鉄だ。
あの丁稚だった。こんどは畑道で鍬をかついでいた。
今ではもう、丁稚ではなく、手代のような風格を帯びるほどになっていた。腰が据わり、手も指もたくましくなっていたが、どこか頑なな眉のかたちに、あのとき里芋の葉の下で震えていた面影が残っていた。
わたしはまた、人の姿をとった。今度は旅の薬売りだ。目に赤い隈を入れ、背に大きな四角の箱を担ぎ、鈴を鳴らして彼に声をかけた。
「おや、これは珍しいところに真面目な若衆。顔に疲れが出ているな。良い薬がある」
彼は少し警戒したように目を細めた。
「お薬より、お名前を教えていただきたく思いますが」
わたしはひと思案した。
「名前なんぞは、何でもよい。権兵衛でよければ」
「なら、お名前は諦めましょう、権兵衛さん。でも、現状、山の鹿が田を荒らして困っておりまして、何かよい方策はないものかと」
鉄砲は許可制で使えない。
わたしは荷を背負い直した。
「ほう、それはただ事ではないね」
田圃は主人の自家用米を作るためのものらしい。田仕事は丁稚の担当だ。
「鹿が畦を踏み抜き、水を逃がすんですよ。もう三度も埋め戻しをしたけど、被害は止まない。夜ごとに角で唸るような音がするんです」
わたしは首を傾げながら、空をにらんだ。
「鹿も生きておる。だが、狡(ずる)い奴もおる。ひょっとするとそれは、鹿ではないかもしれんな」
彼は少しだけ太い眉を上げた。
「まさか――狐ですか?」
わたしは少し冷や汗をかきながら、笑みを作った。
「まさか。狐が田を踏み抜くなど」
丁稚が鍬を使い始めた姿に、何となく安心感をおぼえた。
間を置かず、わたしはまた藁屋を訪ねた。
姉は編み物の手を休め、わたしの顔を見るなり言った。
「その目は、獣の匂いを嗅いだ目だね」
畦の様子を伝えると、姉は小さく頷き、湯呑を口に運んだ。
「狸だろうさ。あいつらは必ず、水を逃がすところからやる。荒らすだけじゃない、境界を緩めるのが狙いだよ」
確信がひとつ、増えた。
4
その夜、田の畦に座っていると、背後から小石が転がる音がした。
振り返れば、藁笠を目深にかぶった影。
「おまえひとりじゃ、狸の鼻はかわせないよ」
姉だった。ぬかるみに膝をつき、手で土を探った。
「ほら、この指の跡。狸は、押してから崩す」
月明かりに照らされたその跡を、わたしはしっかり頭に叩き込んだ。
待ちぼうけを食わせられたが、次の晩、わたしは姉と共に、ふたたび田の畦に座った。今度は狐本来の姿のまま、里芋の葉の上に腰をおろし、ぬかるむ土に耳をすませる。
奴らは、ただ田を荒らすのではない。人が作ったものなら何であれ壊すほうを好む。人と山との間の線を、濡らし、削り、滑らせる。
かつて、峠を越えた先の隣里が、狸の笑い声で荒れ果てた事態を思い出した。
今夜の気配は、あの時の匂いに似ている。
待つうちに――来た。
狸のぬらりとした影が、田の縁から現れた。わたしの気配に気づくと、動きを止め、言葉もなくこちらを見つめてきた。
わたしは声を太くした。
「また、せこい真似をしておるな」
狸は笑わず、目だけが、空洞のように深い闇を抱えていた。言葉ではなく沈黙を武器にする。それは、何も語らずとも揺らぐように、相手の心に疑念を植えつけるやり方だ。
ついに、唇の端を上げて言った。
「狐のくせに、二匹して、人に肩入れか。山を捨てたか?」
わたしはぐっと腹に力を入れた。
「それは、ひがみというものだ。どうして畔を壊したりするんだ?」
狸はふっと身を翻した。
「田を壊せば、人は山に憎しみを抱く。そうすれば、山もまた、牙を見せる。狐だろうと、例外じゃない」
わたしの姉がいたためか、それきり、狸は消えた。ぬかるみに残った足跡は、月明かりでじわりと蒸され、やがて闇に吸われた。
5
翌日、もう青年と呼ぶべき丁稚は、わたしに問うた。
「薬売りの権兵衛さん、本当に、狐の嫁入りってあるんですか?」
――まだ同じ疑問を抱いている。よほど気になるらしい。
少し時間をおいて答えた。
「ある。だが、祝言ではない。別れだ。山を去る者の、最後の灯りだ」
彼は少し考えるように黙ってから、決意を固めた風に顔をあげた。
「ぼくが山に入って、鹿を追い出せばいいですか?」
わたしは、とっさに頭(かぶり)を振った。
「いや。山に入ってはいかん。狐が守るものは、人の無知だ。知ろうとしないことが、人と山を分けておる」
難しい顔つきをしたが、やがて彼の頭が上下に振れた。
「噂によると、酢を撒けば、鹿は嫌がって近づかないそうなんです」
そのまま、ふと家の方を見て、声を落とした。
「――女中がいるんです。怖がって泣くもので」
その理由には覚えがあった。わたしは荷を解いて、酢の素を手渡しながら、厚意の印に、手を横に振った。
それからというもの、彼は畦に酢を撒き、音を鳴らす竹筒をいくつも設けた。
鹿は嫌がって近づかなくなった。
小さき者は、霧や鳴き声に敏(さと)い。人も獣も同じで、何の差もない。
そしてある夜、わたしは再び行列を見た。
狐の嫁入り――ではなかった。
それは狸たちの撤退の儀だった。提灯も持たず、里芋の葉も差さず、ただ霧の中を静かに移動する獣たちの列。
それを見届けながら、わたしはそっと里芋の葉を被った。
人と山との間に、また一本、細い線が引かれた。
わたしは、その線の上に立ち続ける。狐とは、そういうものだからだ。
6
山に戻ろう、と、ふいに思った。ここは人事が多すぎる。
それが「今度こそ」だったのか、それとも、ただひとときの気の迷いだったのかは、自分でもよく分からぬ。
けれど、そのときのわたしは、妙に疲れていたのだ。
田畑には平穏が戻り、あの青年の顔にも、ようやく笑みが定着し始めた。
狐が人の営みに関わるに当たっては、長居をすべきではない――そう言ったのは、かつての師だった古い尾持ちだ。
「手を貸せば貸すほど、尻尾を踏まれる」
そう言って、彼はあるとき忽然と姿を消した。人だったら、星になったというのだろう。
わたしは、山の予備穴に戻った。風は冷たく、土は乾いていた。久しぶりに尾を解き、丸くなって眠った。
それでも耳には届いてくる。木々の隙間を縫って、村の声が。
「酢のおかげで、鹿が来なくなった」
「狐火を見たら、願い事が叶うらしいぞ」
声の主は決まっている。あの青年だ。
村の者たちが笑うたびに、その中に彼の名が交じる。夜な夜な祠に立つ姿も、山から見える。
ある日、祠の奉納台に、ふっくらと炊かれた豆飯が供えられていた。里芋の葉で、ていねいに包まれている。
誰が置いたかなど、考えるまでもない。
――けれど、それが「呼び声」であったのか、「別れの印」であったのか、そのときは判じかねた。
そのためか、わたしの足は、また山を下り始めていた。
狐とは、本来、名もなき風のようなものだから。
7
秋が来て、丁稚の田は黄金色に染まった。
わたしは姿を見られないよう、遠くから見守っていた。
すると、ある晩、何かが変わった。
月のない夜――里の外れで、ひとりの若い娘が泣いていた。あの女中だ。
すすり泣く娘の傍らで、急に草の揺れる音がした。夜の帳の下、獣の足音が湿った地面を踏み鳴らしている。
娘は荷を抱きしめ、声を呑んだ。
低く唸るような気配――それは、山の鹿ではない。鼻の鋭い、牙をもつものだ。
闇の奥から、細長い影がすっと現れ、じりじりと距離を詰めてくる。
娘の指が震えながら、荷の端にしがみついたとき――まさにそのとき、ふいに風が巻き、木の枝をはじいて、何かがその獣の足元に落ちた。
それは、小さな石だった。もちろん、投げたのはわたしだ。
獣がぴたりと動きを止め、鼻を鳴らして、音の主を探るように首を回す。
その隙に、娘は後ずさりし、木の陰へと滑り込んだ。
獣はしばらく様子を伺っていたが、やがて山の斜面へと姿を消した。
木陰の娘は、息をひそめたまま、祠の灯りを遠目で見るような仕草をした。
わたしは久しぶりに人の姿をとった。旅の絵師として。
まず、声をかけ、それから近づいて、安心させてやった。
背中には大きな結びの荷、裾は泥に濡れ、足は草鞋のまま裸足に近かった。
話を聞けば、奉公先で無実の盗みを疑われ、居場所を失ったという。
「嘘じゃありません、本当にわたしじゃないんです。けど、もう誰も信じてくれない」
わたしは言った。
「盗んでいない! あの女将を相手に、無実を証明するのは、なかなか大変だぞ」
事実は一つでも、解釈はつねに幾通りもある。狐には、事実こそが大事だ。
わたしが口を閉じるや、娘は言った。
「狐の神さまに頼んだんです。どうか、あの人だけはわたしを信じてくれるようにって」
あの人、というのは、彼のことに違いない。
事情が複雑そうだったため、また姉の手元に預かってもらった。
8
翌朝、わたしは青年のもとに現れた。今度の姿は、白い襟巻きをした老侍。
彼は一瞬、なにかを思い出すように目を細めたが、問いただそうとはしなかった。
「若い衆、祠で願うのはいい。だが、願いを託された者のことも、考えねばならぬ」
彼は驚いたように目を見張った。
「なんと。神様には迷惑だったわけですか」
わたしは少し前かがみになって、声音を下げた。
「村の娘が、おぬしにすがったぞ。狐の神に託してまで」
彼の顔色が変わった。
「わたしは、あの子を疑ってはいません。ただ、言えなかっただけです」
図星だった。
わたしは静かに頷いた。
「ならば、言え。信じている、と。神様じゃあるまいし、口を持っているだろ。それとも狐の霊魂にでも頼みたいか? 人が言葉で救うほうが、何倍も難しいか?」
青年は立ち上がった。
小さな決意を湛えた背中を、わたしは黙って見送った。
それから三日後。女中は戻され、冤罪は解けた。
盗みを働いたのは別の者――実のところ家の息子――で、彼女の潔白は証明された。ドラ息子が小判を懐に入れる現場を押さえられたという。
その晩、祠には豆飯と酒、それから小さな銀の鈴が供えられていた。
古狐の介入が、また一つ、終わったのだ。
だが今度は、誰もいなくならなかった。
お礼参りから帰ろうとする女中に、旅の絵師が声をかけた。
「罪を着せられなくて良かったな」
女中が深くお辞儀をした。
「あの人のお蔭なんです」
わたしは、同族かもしれないというかつての閃きを思い出した。そこで、絵筆で空をなぞった。
「こっち側で、上手く生きていけるようにしてもらったわけだ」
女中が一瞬、鋭い顔つきになって、口を尖らせた。
「境界に生きる者は、どちらにも属さないんです」
「どうして、そう思うようになったのだ?」
女中の顎がぐっと締まって、小首がかしいだ。
「幼い頃、まだ名を持つ前のわたしは、よく山に呼ばれるような気がしていたわ。誰もいないはずの森の奥で、ひとつぶの狐火が道を照らすのを見たのも、一度や二度ではなかったし。それを他に言うと叱られた。そんなもの見えるはずがない、って。でも、わたしには見えた。それが怖くなくて、むしろ懐かしかったのを覚えているわ」
わたしの閃きは裏付けられたようなものだった。
「それは、人間とは思えないほどの、鋭敏な感受性だなあ」
「あの時の光が、いままたわたしの前に灯るわ。きっと、わたしはあの日から、境界にいる者だったのでしょ」
山に戻る前の日、わたしはもう一度、祠のほうを見に行った。
女中の影が、石段を数えながら上っていた。瞳には灯りがキラリ反映した。下駄の音を抑えながら、手には小さな木の人形だ。
姿を眺める限り、何かを、誰かに語りかけているようだった。
――人は時おり、風に話しかける。
その風に、わたしが混じっていたとしても、知らぬ顔をするだけだ。
すると、祠の裏手から小さな足音がした。細く乾いたその気配は、老婆――わたしの姉のものだった。
人の姿をとった彼女は、藁の包みを手にして、女中の傍らに腰を下ろした。
女中は少し驚いたように横を向いたが、すぐに目を伏せた。
老婆の声はしわがれている。
「泣くな。風は、涙の音で濡れる」
どこか親のような優しさがこもっていた。
女中は木の人形をじっと見つめたまま、ほろりとこぼした。
「誰も、わたしのことなんて、見てないようで」
老婆が笑った。
「見ている者は、見せないものさ。狐もそうだ。――それに、見える者は、あんたのような子じゃ」
女中は可愛らしい目を少し上げた。
風が一度、祠の鈴を鳴らした。風はわたしが送った。
それからというもの、女中は祠に来るたび、小さな木彫りの人形を置いていくようになった。
誰かに向けた贈り物ではなく――自分が見えている証のようでもあった。
9
夜の帳がゆっくりと下り、風に混じって落ち葉が鳴いた。
季節はもう、晩秋だ。山の紅葉はとうに落ちて、裸の枝ばかりが空を刺していた。
ひさしぶりに里へ降りると、祠のまわりには落ち葉の絨毯が敷き詰められていた。
かつて酢が撒かれ、狸と霧の夜をくぐったあの頃合い。
――もう、誰もいないだろう。
そう思っていた。
けれど、灯りがあった。かすかな火が、祠の脇で揺れている。
薬売りに姿を変えて近づくと、彼がいた。
手製の焚き火を囲み、火を崩さぬように薪を組み直していた。狐の気配に気づいたのか、それとも、最初からわかっていたのか。
彼は言葉を発してから、にっこり笑った。
「今年も、来てくれるかと思って」
少しやつれたようにも見えたが、その目は変わっていない。まっすぐで、曇りがない。
わたしは、諸国巡りの薬売りだからな、とは返さずに、かねて言葉にしたかった話をした。月に嫁いだ狐が満月の時だけ婿に会える、という昔話だった。
青年が顔を空に向けた。
「狐の仕来りも、月に対しては従属しているんですね」
わたしは火のそばに薬箱を置いて、首を横に振った。
「月に惚れるとはそうしたものさ。あらゆる困難が一挙に押し寄せてくる。それでも、障害を乗り越える力が湧くのが、惚れた腫れたの核心なのさ」
青年の頬に、実に微かな歪みが走った。
それを取りつくろうように、彼は、懐から紙包みを取り出すと、火で少し炙った。
「豆飯。去年と、ちょっとだけ違って、よくできた」
わたしは、少し焦げた匂いを吸い込んだ。
「あの子も喜ぶんじゃないか。豊作だし、祠にも奉納できたし」
青年が軽く飛び上がったような仕草をして、首を傾げた。
「あの子? そうか、まだ、食べさせていなかったんだっけ」
人の営みの匂い――それはどこか、山とは違った、里人らしい温度を持っていた。
10
冬の香りは、土の埃から始まる。
その朝、山の端にうっすらと白いものが見えた。
祠のまわりも、霜が降りて静まり返っていた。誰の気配もなく、焚き火の跡も消えている。
わたしはしばらく佇んで、風の匂いを嗅いだ。
霜の下、燃えさしはすでに冷えきっていたが、どこかに彼の匂いが残っていた。
空は淡く、雲は低い。
わたしはひとつ大きく息を吐くと、踵を返した。
山道に入る手前、祠の裏の竹林で、ひとつのにおいがして立ち止まった。鉄と油、干からびた藁、そして人の匂いが微かにただよう。
――罠だ。
目を凝らすと、落ち葉に紛れて、それはあった。獣の足を挟むよう、鋼の輪が口を開いていた。
周囲には、踏み固められた土の跡。ここを誰かが何度も通った形跡がある。
村人たちが仕掛けたのだろう。狸を狙っての技に違いない。
今年もまた、何か厄介な真似でもしたのか。
風が吹いて、木の皮がめくれた。
わたしはしばらく、その罠を見つめていた。
――狸は踏むだろう。
そう思った。
それが報復の狩りなのか、それとも、この時期の慣わしなのか。あるいはただの遊びか。わたしには分からない。
けれど、こういう時、たいてい誰かが泣く。
雪が尾に触れた。
わたしはその場を離れ、山の闇へと歩き始めた。
11
数日後、罠にかかったのは、案の定、狸だった。
血に濡れた縄を見て、わたしは一瞬だけ目を閉じた。
その狸は、かつて山を荒らし田の畔を壊した張本人だった。人の世界に手を出し、わたしと睨み合った過去がある。
まさか、こんなかたちで落ちるとは。
奴は、つい先の夜にも、里の畦に笑い声を残したという。言葉ではなく、意志だけを動かす。それは、狐よりも人に近い。だからこそ、危うい。
わたしは、あの目を覚えている。境界を壊すことこそが、奴の悦びだった。
夜になると風が吹いた。
狐の嫁入りにはならなかった。誰も消えなかった。まだ。
ある朝。祠の前に、新しい石が置かれていた。深い彫りの文字で、「風の神、此処にあり」とあった。狐大明神のつもりだろう。
誰が彫ったかは、知らない。
けれど、その夜、狐の行列が出た。炎も鳴き声もない。ただ、白い煙のように、静かに斜面を渡っていく。
わたしは混ざらなかった。見送る側にいたのだ。
山と里の境界に棲み、化け、消え、時に残る。わたしはそうしてきた。
姉のように村外れに住むやり方もあったろうが、きつ過ぎて、出来ない相談であった。
12
その晩もまた、雨だった。
ただの雨ではない。空が透けるような白雨――狐の嫁入りにふさわしい、奇妙な光を帯びた雨だった。
わたしは祠の裏手にいた。
姿はとっていない。ただ、雨に濡れながら、じっと耳を澄ませていた。
――この雨を待っていたのは、わたしだけではなかった。
誰かがやってきた。
草を踏む音。太鼓も笛もない。提灯もない。けれど確かに――嫁入りの気配がした。
ひとりの青年が現れた。
肩に蓑をかけ、片手に、狐面をぶらさげていた。
姉の話によると、彼は、季節が移るたび、焚き火の跡を清め、豆飯を供え、ただ静かに座る夜が続いたそうだ。
何かを待っていたのかもしれない。あるいは、誰かの沈黙の中に、自分の答えを見つけようとしていたのかもしれない。
里での仕事は順調でも、心の隙間が埋まることはなかったようだ。
彼は、祠の前に立つと、ぽつりと声を落とした。
「狐大明神さま。――あの日、俺に言葉をくれた娘が、消えました」
わたしは、耳をそばだてた。
「村の者は山に呼ばれたと噂する。でも、あんたでしょう。――いや、ちがうな。あの娘が、自分から行ったんだ。分かってる」
その娘の顔が、よみがえった。ややうりざね顔で眉の細い、綺麗な目をしていた。
獣に狙われ、ひとり佇み、わたしに気づいたあの目。
「視えていた」のだ。山と里の狭間にいる、わたしのようなものが。
「――あの子は、言ってた。『境界にいる者が、一番さびしい』って。だから俺、あの子に伝えに来たんです」
彼は、狐面を奉納台にそっと置いた。
「俺が婿入りします」
わたしは一瞬、息を飲んだ。
――狐が嫁ぐのではない。人が狐に婿入りするというのか?
わたしは姿をとった。
小柄な、旅姿の若侍――あの日のままの姿で、祠の影から身を晒した。
「それは、愚かな行為だぞ。人が山に入れば、もう帰れぬ。――あの娘のように」
青年は驚いて、一歩後退ざった。わたしの姿を認めると、かすかに笑った。
「お武家さんでしたか。――俺は、帰る気なんて、さらさらない。俺は、あの子が見たものを知りたい。あの子が選んだものを、受け継ぎたい。――あの子の隣に、いたい」
雨音が強くなった。雷は遠い。だが空の匂いは、あの日を思い出させるものだった。
丁稚が商家に戻った日の夜、狐の嫁入りの満月が出たとは――あの頃からすでに女中との縁があったのだろうか。
わたしの沈思を破るように、青年が声をあげた。
「もう、人の名前で呼ばれるのは、やめました」
わたしは、岩のように彼の言葉を受け止める。
「名を捨てるならば、身分も捨てる羽目になる。自由だが、危険でもあるぞ」
わたしはキツネの仕来りの内実、つまり自然の摂理を再度説いた。
青年の眉がピッと音を立てて、寄った。
「そんなものは、貧富差や身分差に比べたら、障害のうちに入りませんよ」
それほどの心つもりなら名なき者同士、どこまでも歩いていけるだろう。
「よい覚悟だ」
わたしの激励に合わせるかのように、背後で、もうひとつの気配が立った。
振り返ると、薄衣を羽織った娘が立っていた。あの目をした娘――もう人ではない、けれど完全に狐にもなっていない。尻尾がまだ衣服の中で膨れている姿だ。
娘は、ひと呼吸してから言った。
「このひとは、連れて帰ってあげてください――境界にいるのは、並大抵じゃないわ」
その声は、風に溶けるような響きを持っていた。
わたしは一瞬だけ、彼女の瞳を覗いた。そこに映っていたのは、火影だった。かつての夕暮れ、祠の前で灯りに浮き上がっていたのと同じような。
「見える者は、選ばれるのではなく、見た時点でもう、戻れないんだよ」
娘が微かに笑った。
「だから、わたしはもう、戻らない。ただ――この人は、違う」
わたしは、ほんの短く頷いた。
風が一陣、祠の鈴を鳴らした。
娘はそれに応えるように、歩を祠の奥へと進みながら言った。
「狐は、人を騙すってみんな言うけど。わたしは、いつも守られてた」
わたしの尾が着物の下で我知らず震えた。
娘は振り返らず、霧のように祠の奥へと消えた。
その瞬間、雷光が走った。風が木々を揺らし、雨が音をたてて踊りはじめた。
祠には、山の気配が濃くなった。
わたしは青年に首を向け、念を押した。
「名を捨てよ。衣を捨てよ。里を捨てよ。困難の渦だ――それでも、来るか」
青年は、迷わずうなずいた。
「もう、雨が止みましたね。本当の狐火だ」
その夜、狐は嫁がなかった。
人が、狐に婿入りを果たしたのだった。満月ではなかったが、櫛形の灯りが空の端に浮かんでいた。間もなく、黒い雲に隠された。
翌朝、祠の前には誰の姿もなかった。ただ、伏せられた狐面がひとつあるのみ。
里では、二人も若い衆が消えたと、しばらく騒ぎになった。いつしか、その名を口にする風の声もわたしの耳に届かなくなった。
まもなく、祠の前に、小さな豆飯が二つ、並んで供えられた。境界を越えた者たちへの、ささやかな餞(はなむけ)だった。
姉から調達したもので、わたしの仕業であるとは、誰も気づいていない。
エピローグ
春の光が、霧の繭をほどいていた。
祠の前には、風の爪あとをなぞるように、ふたつの古い木像が並んでいる。目も名もない。けれど、その沈黙が、最も多くを語る。
山は、ひとつ息を吐いた。空気がやわらかく折れ曲がり、尾の気配が落葉のうえをそっとなぞった。
誰一人、その痕跡を気にかけるものはいない。だが、見えぬものこそが、変化の旗を揚げる。
境界とは、陸と水のあいだに張られた細い糸のようなものだ。踏み越えた者は、元の岸に戻ろうとしても、足が水になってしまう。今は亡き姉の古狐もそうだったように。
木像に刻まれた線が、朝日を吸って薄くきらめいた。それはまるで、春の涙のようでもあった。
やがて風が祠を抱き、鈴が、誰にも聞こえぬ音で鳴った。
わたしは、声を立てず、ただ尾をなびかせた。
――世界とか時代とか、新しくなるとき、音は鳴らず、名は呼ばれず、けれど、何かが確かに始まるものだろう。
そうした平凡に見える今日もまた、誰かが、自分のかたちを変えるのだ。
完
[ライタープロフィール]
野上勝彦(のがみ かつひこ)
1946年6月、宮崎県都城市生まれ。10歳の秋、志賀直哉と出会い、感銘を受ける。20歳のとき関節リウマチを発症、慶應義塾大学独文科を中退。数年間、湯治に専念。画家になるか作家になるか迷った末、作家になろうと決める。長編小説20編以上の準備をするが、短編小説数編しか発表できず。31歳のとき、文学を学び直すため、早稲田大学第二文学部に入学。13年浪人という形になった。英文学専攻、シェイクスピア学を中心に学ぶ。足かけ5年間、イギリスに留学。留学中父親を亡くす。詩人のグループに属し、英詩を書き、好評を得る。1989年末、帰国。教員となる。2010年、本務校を退職。同僚先輩から借りた本代1000万円を完済。2017年、非常勤講師をすべて定年退職。2018年、最初の評論集が『朝日新聞』書評欄で取り上げられる。最初の長編小説を完成させたのが2019年。いずれも出版に際し、グリム童話研究家金成陽一氏の紹介により河野和憲社長(当時編集部長)のお世話になって、現在に至る。12歳の時、最初の短編小説を書いて以降、題材を2000本以上書き留める。2024年、短編・掌編の執筆戦略を練り、題材帳をもとに書き始める。現在、未発表短編1200作を数える。
【単著】『〈創造〉の秘密――シェイクスピアとカフカとコンラッドの場合』彩流社、2018年。『暁の新月――ザ・グレート・ゲームの狭間で』彩流社、2019年。『始源の火――雲南夢幻』彩流社、2020年。『疾駆する白象――ザ・グレート・ゲーム東漸』彩流社、2021年。『マカオ黒帯団』彩流社、2022年。『無限遠点――ザ・グレート・ゲーム浸潤』彩流社、2023年。
【共著】『シェイクスピア大事典』日本図書センター、2002年。『ことばと文化のシェイクスピア』早稲田大学出版部、2007年。The Collected Works of John Ford, Vol. IV, Oxford: Oxford University Press, 2023.
【論文】‘The Rationalization of Conflicts of John Ford’s The Lady’s Trial’,Studies in English Literature, 1500-1900,32,341-59,1992年、など37本。詳細についてはウェブサイトresearchmapを参照。
【連載】『近代神秘集:生きもの編』、ウェブマガジン『彩マガ』彩流社、2025年4月16日より。