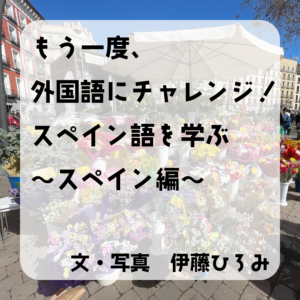第8回 トレドを愛した画家、エル・グレコに酔いしれる
文・写真 伊藤ひろみ
外国語学習に年齢制限はない!――そう意気込んで、国内でスペイン語学習に挑戦したものの、思うように前進しない日々が続いていた。そんな停滞に歯止めをかけるべく、現地で学んでみようとメキシコ・グアナフアトへと向かったのが2023年2月。約1か月間、ホームステイをしながら、スペイン語講座に通った(くわしくは、「もう一度、外国語にチャレンジ! スペイン語を学ぶ ~メキシコ編~」をご参照ください)。
1年後、再び短期留学を決意する。目指したのはスペインの古都トレドである。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
<第8回> トレドを愛した画家、エル・グレコに酔いしれる
トレド旧市街の西側に位置するユダヤ人居住区は、独特の町の雰囲気を持っている。博物館やシナゴーグなどを見学しながら、個人的にも大いに刺激を受けたエリアだった(詳細は第7回を参照ください)。この地区でさらにおすすめしたいところがある。
誰もが気軽に鑑賞できる無料観覧の日
スペインは名だたる画家を数多く輩出している国であるが、ベラスケス、ゴヤと並ぶ三大画家のひとりと言われるのがエル・グレコ。トレドにある美術館や教会など、いくつかの場所で彼の作品に出会うことができる。
そのひとつが、ユダヤ人居住区にあるエル・グレコ美術館(Museo Del Greco)。マルタが「今日行ってみたら」と教えてくれたので、そのアドバイス通り、行動開始。先日訪ねたセファルディ博物館(Museo Sefardi)のすぐ横にあることを地図で確かめ、ぶらぶら歩いて美術館を目指す。

エル・グレコ美術館の入口。左の建物内に展示室がある
「ようこそエル・グレコ美術館へ」と受付にいたスタッフが歓迎の意を示す。入館料を支払おうとしたら、にっこりしながら「Hoy es el día de entrada gratuita.(今日は無料開放の日ですよ」 と返した(entradaは「入場、入り口」などの意味を持つ女性名詞、gratuitaは「無料の」という形容詞の女性形)。
そういえば、マドリッドの美術館・博物館でも、そんな日があったことを思い出した。そのタイミングに合わせて観光客などがどっと押し寄せるので混雑は避けられないが、多くの人が気軽に美術にふれる機会を増やすという意味では、ありがたい取り組みである。すべての美術館ではないものの、場所によってはこうした日を設けたり、複数の美術館・博物館が見学できる共通のパスも販売したりしているので、上手に利用したい。マルタが今日行くことを薦めた理由も納得できた。 (2024年2月時点でエル・グレコ美術館の場合、通常入館料は3ユーロ。土曜の14時以降と日曜日が無料開放の日。最新情報を確認してください)。

エル・グレコが活躍した時代の家屋を再現して造られた建物
入口で荷物を預け、外廊下を抜け、別棟の建物内へ入る。家具や調度品が置かれたいくつかの部屋は、エル・グレコのアトリエや書斎、寝室などを再現したもの。ユダヤ人居住区に住んでいた彼の家屋をイメージして造られたという。
そして展示室へ。すべて同じ大きさのキャンバスを用い、中央にイエス・キリストを配し、ずらりと横に並ぶ形で展示されていたのが「十二使徒」。十二使徒とは、キリストの弟子たちの中から特別に選ばれたペトロ、ヤコブなどのこと。キリストの教えを学び、布教活動を行った超重要人物たちである。何かを訴えるような視線、物憂げな表情など、それぞれの個性とともに、生き生きとしたエル・グレコの世界が広がる。

シリーズで鑑賞したい「十二使徒」。独特の体のバランスがエル・グレコの特徴のひとつ
「トレドの景観と地図」もここで出会える。アルカサールや大聖堂などトレドの町の全景を描くとともに、手前右には、トレドの地図を広げる少年を配し、聖母マリアとトレドの守護聖人が天上に舞っている。これらを1枚に描くというのもなかなかユニークな発想。この作品を見るかぎり、今もトレドの風景はさほど変わっていない印象を受ける。
ド迫力の作品に込められたメッセージとは?
さらに、エル・グレコの世界を味わうために、サン・トメ教会(Iglesia de Santo Tomé)へ
足を運ぶ。ここには、「オルガス伯の埋葬」が展示されているからだ。
まず驚いたのは、高さ480 cm、幅360 cmという大きさ。超がつくほどの迫力を持つ作品!
オルガスの領主の魂を神が救済するという場面である。上部に天上、下部に地上という異なる世界をひとつの作品に仕上げた。オルガス伯のほか、マリアとヨハネ、天から舞い降りた聖人たち、さらにそれに立ち会う人々……。
この作品には、いったい何人が描かれているのだろう。参列者の人数も多く、それぞれの表情も豊か。この中に、エル・グレコ自身や彼の息子もこっそりしのばせているという説もあると聞き、さらに興味が増す。
展示室はこの1点のみを飾っていた。作品自体が大きいので、外部に持ち出すことはできず、観賞できるのはここでのみ。この絵画を一目見ようとやってくる人々で、室内は常にごった返していた。彼らをかき分けながら、遠くから眺めてみたり、近寄ってディテールに注目してみたり。いったいどれほどの時間をかけてこれを完成させたのか。彼はどんな思いでこの作品を描いたのか。

トレドのサン・トメ教会でのみ鑑賞できるエル・グレコの超大作
ギリシャからイタリアへ。さらにトレドで花開いた特異な才能
エル・グレコは1541年ギリシャ・クレタ島に生まれた。ヴェネツィアやローマなどを経て、1577年からトレドで暮らし始める。
本名はドメニコス・テオトコプロス。エル・グレコとは、スペイン語の男性定冠詞、el とイタリア語のGrecoの合成語で「ギリシャ人」を意味する。
彼はキリスト、マリア、ヨハネ、聖人などとともに、多くの宗教画を描いた。「オルガス伯の埋葬」のように、その画力もさることながら、1枚のキャンパスに異なる世界を同時に描くという独特の世界観、物語性も併せ持つ。
1614年に亡くなるまでトレドで暮らし、トレドを愛した画家。その一方、ギリシャ人としてのアイデンティティも消し去ることがなかったのか、作品には、生涯を通じてギリシャ語による「ドメニコス」とサインしたという。
「どうだ、参ったか!」とエル・グレコの声が聞こえるほどのパワーを持つ「オルガス伯の埋葬」。鑑賞後は、彼が暮らしたタホ河畔で、しばしクールダウンしたくなるほどだった。
[ライタープロフィール]
伊藤ひろみ
ライター・編集者。出版社での編集者勤務を経てフリーに。航空会社の機内誌、フリーペーパーなどに紀行文やエッセイを寄稿。主な著書に『マルタ 地中海楽園ガイド』(彩流社)、『釜山 今と昔を歩く旅』(新幹社)などがある。日本旅行作家協会会員。