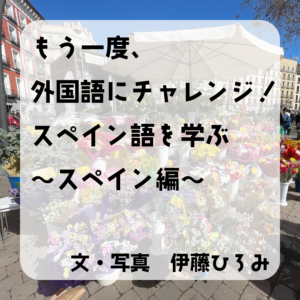第12回 城壁に囲まれた町から
文・写真 伊藤ひろみ
外国語学習に年齢制限はない!――そう意気込んで、国内でスペイン語学習に挑戦したものの、思うように前進しない日々が続いていた。そんな停滞に歯止めをかけるべく、現地で学んでみようとメキシコ・グアナフアトへと向かったのが2023年2月。約1か月間、ホームステイをしながら、スペイン語講座に通った(くわしくは、「もう一度、外国語にチャレンジ! スペイン語を学ぶ ~メキシコ編~」をご参照ください)。
1年後、再び短期留学を決意する。目指したのはスペインの古都トレドである。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
<第12回> 城壁に囲まれた町から
誰から町を守るのか
私がトレドに来て最初に覚えたスペイン語の単語は、ムラージャ(muralla・城壁の意味)だった。マルタが家の近所を案内してくれたとき、それを指さしながら説明してくれたからである。
トレドは東から南、さらに西へと三方がタホ川(Rio Tajo)に囲まれているが、北側は陸続き。城壁は主に旧市街の北側を中心に築かれている。マルタ宅が旧市街の北に位置していたため、毎日のようにそれを見ながら過ごすことになった。

旧市街と新市街を分かつ強固なムラージャ。修復を重ねながら今に至り、トレドを印象的な景観にしている
城壁は高く頑丈に築かれていて、外からの侵入を防いでいる。旧市街に入るには、北東側にあるビサグラ門(Puerta de Bisagra)か、北西側にあるカンブロン門(Puerta del Cambrón)のいずれかを通らなければならない。
マルタ宅のそばにはビサグラ門があり、何度もその門をくぐった。城壁の北にある新市街側には、太く頑丈そうな二本の円柱に挟まれるようにしてアーチ状の門がある。その門の先には、さらにもうひとつ。こちらは三角屋根の四角い塔がついた門が見えてくる。これらの門はあくまで人が通るためのもの。現在はその横の城壁の一部を切り崩し、車両通行用としている。


ビサグラ門。新市街側(上)と旧市街側(下)との二重の門。新市街側の門の上には市の紋章が飾られている
ちなみに、旧市街の一部の通りは車も入れるが、道幅が狭く、一方通行がほとんどである。観光バスなどの大型車両で訪れた観光客は、城壁の外にある大きな駐車場で下車し、徒歩で旧市街を観光することになる。
ビサグラ門をくぐって南に進み、急な坂道をのぼると、さらに別の門、太陽の門(Puerta del Sol)がある。14世紀に建築されたムデハル様式(イスラム美術を取り込んだキリスト教建築様式)の門である。眼下に広がる新市街と太陽の門とのコントラストが、トレドらしい景観を織りなしている。とりわけ夕暮れ時が美しい。

町を象徴するモニュメントのひとつ、太陽の門
タホ川を越えて旧市街へ入るには
トレドへ入るには、これらの門をくぐり抜けるか、タホ川を渡らなければならない。川の両岸は結構深い崖になっている。タホ川はトレドの水源でもあったが、天然の要塞としても重要な役割を果たした。
タホ川にかかる橋のひとつは、東にあるアルカンタラ橋(Puenta de Alcántara)。太い橋脚と大きなアーチが特徴の重厚な橋である。この橋はローマ時代、2世紀初めの創建だが、その後何度も改修されたようである。目の前にあるのが当時の姿のままではないにしろ、今日まで使用可能な橋を建築できるローマ時代の土木技術に感嘆せざるを得ない。
過去においては熾烈な戦いの場であったかもしれない。あるいは、ここで非業の死を遂げた者も少なくなかったかもしれない。今は観光客たちがこの橋を行き来する姿を目にするだけで、おだやかな空気に包まれている。

全長約200mのアルカンタラ橋。車両は通行できず、徒歩のみで渡ることができる
モスク×カトリック教会=博物館?
太陽の門のそばに、興味深い場所がある。メスキータ・デル・クリスト・デ・ラ・ルス(Mezquita del Cristo de la luz・光のキリストのモスク)と呼ばれている。なぜキリストのモスクなのか、不思議に思われることだろう。
もともとここは10世紀後半に造られたモスクだった。当時はイベリア半島においてイスラム教が勢力を拡大しつつあったころ。ここトレドにも、ムスリム様式の祈りの場が造られたのであろう。その後、ムデハル様式を取り入れて増築し、レコンキスタ(国土回復運動)後、キリスト教教会へ。時代による劇的な変化を遂げた場所となっている。
百聞は一見に如かず。中に入ってみれば、それを実感できる。
馬蹄形のアーチのほか、外観も内部の装飾もイスラム的要素が感じられる造り。全体として存在感があるうえ、装飾は繊細で、技巧的。控え目ではあるが、バランスの取れた美しさである。しかし、そのドーム型天井の下には、イエス・キリストが掲げられているのである。
歴史的建造物を維持し、それを守ろうとする姿勢は評価すべきこと。ならば、イエス・キリストを掲げたりせず、そのまま残すという選択肢はなかったのだろうか。ふとそんな思いにかられてしまった。

異なる宗教のありようを提示しているメスキータ・デル・クリスト・デ・ラ・ルス
ここの入口の前の通りは、ローマ時代のものらしい。また近年の発掘で、ここにローマ時代の採石場があったという報告もなされていると、語学学校のカロリーナ先生が教えてくれた。私は考古学者でも歴史研究者でもないが、壮大な歴史が詰まったような場所として、きわめて興味深かった。
旧市街を取り巻く城壁は、誰から身を守るためだったのか。それぞれの時代に力をふるったものたちが残した遺構を、我々はどのように引き継ぐか、あるいは捨て去るのか。またそれらをどう観光と結びつけるのか。一筋縄ではいかない課題ばかりが頭に浮かぶ。
教会、モスク、シナゴーグ、博物館……。トレドの町歩きは、壮大なスペインの歴史と向き合うことでもあった。
[ライタープロフィール]
伊藤ひろみ
ライター・編集者。出版社での編集者勤務を経てフリーに。航空会社の機内誌、フリーペーパーなどに紀行文やエッセイを寄稿。主な著書に『マルタ 地中海楽園ガイド』(彩流社)、『釜山 今と昔を歩く旅』(新幹社)などがある。日本旅行作家協会会員。