第25回 普通ってなんだ
コバン・ミヤガワ

「普通にうまい」って、それ「普通」なの「うまい」のどっちなの?
「普通」について、しばらく考えた。
誰かと食事をしているとき「おいしい」と口に出して言うようにしている。
それは「おいしい」とか「うまい」とか言う方が本当に美味しい気がするからだ。家でひとりご飯を食べるときも、ボソッと「んまい」と呟いている。
ボクは基本的に味覚がお粗末なので、この世の大抵のものは「おいしい」。外食などしていて「まずい」と思うことなんて、数年に一度あるかないかだ。
ここ数年ではっきりと「まずい」と思った食べ物といえば、近所の中華料理屋で食べた焼きそばである。ソースの色はしっかり付いているのに、まるで味がしない。ほのかにソースの香りがするだけで、塩気など全くない。出来上がった焼きそばを、一度水で洗った様な味がした。一緒に行った知り合いと「これはまずい」と顔を見合わせ、笑いがこみ上げた。
人間は、本当にまずいものと出会ったとき「笑い」が出るんだな。
先日も、友人とお店でご飯を食べていた。
いつものようにパクパク食べ「うまい」と言う。ふと友人に「それうまい?」と聞いてみた。
「ん、普通にうまいよ」
「普通にうまい」なんて、いままで何度も聞いたことのあるセリフだ。でもその日に限っては、その一言がすごく気になってしまった。
「普通なの? うまいの?」
「いや、うまいよ」
「じゃあうまいだけでよくね?」
「ま、まあね。おいしいです」
「よろしい」
なんだかめんどくさい恋人みたいじゃないか。
しみじみと、食事に対する「普通」という言葉について考えた。
「味」に対して「普通」が存在しない、ボクのような人間からすれば、不思議な言葉だ。「普通」な食べ物は「おいしい」に分類されるからだ。今や「ラーメンバカ」と化した弟は、昔、母の料理に対して「普通」と言っていた記憶がある。確かに弟は、食事に対するこだわりが強かった。なにせ、高校の弁当に、味噌汁を要求していたくらいだ。冷凍食品で喜んでいたボクとは大違いである。
作った料理に「普通」と言われたらイラッとするだろうな。もしかしたら「まずい」よりもイラッとするかもしれない。
このお粗末な舌は、なんて幸せなのだろう。
しかし「普通にうまい」という言葉も、確かによく耳にするわけで。
「普通にうまい」は聞いても「普通にまずい」は聞いたことがない。そう考えると「普通」は「おいしい」と「まずい」の間にあるわけではない。
つまりは「想像通り」という意味なのだ。「想像した通りにおいしい」が「普通においしい」と略されているのだ。略語なのだ。
「普通にまずい」と言われないのは、そもそも料理に対して「まずい」ということを想像していないからだ。
中華料理屋の焼きそばだって、「美味しそうな見た目」でありながら「味がしない」からまずかったのだ。あくまでも想定していない味だったから、まずかったわけである。
最近は「普通」という言葉が便利すぎて、言われたほうが推測しないといけない。「普通」の使いすぎには気をつけないといけませんね。
ところで、音楽についても「普通」という言葉を当てはめてみる。
「普通の音楽」ってなんだろう。
しばらく考えたが、答えなんてなかった。音楽に「普通」は存在しないのだ。そもそも「普通の音楽」だなんて言ってしまったら、失礼になってしまう。
しかし「掴みどころのない」という意味での「普通の四人」が、化学反応的に爆発しているバンドならある。
SUPERCAR(スーパーカー)
スーパーカーには、どのバンドにもない魅力がある。独特である。しかし「ここが良い!」と言い切れない不思議さもある。どこが良いか分からない。
ボーカルもギターも、ベースもドラムも、言ってしまえば「普通」なのだ。
個々を見れば普通なのに、「普通の四人」が集まると、とんでもない融合を起こすバンド。それがスーパーカーである。
今回は「異常なまでに普通」のスーパーカーを掘り下げていきたい。
スーパーカーは、1995年に青森で結成され、2005年まで活動していたロックバンドだ。
結成の仕方も普通である。
「楽器屋の張り紙」
ここがまた普通でイカすじゃないか。ギターのいしわたり淳治が貼った、メンバー募集の貼り紙で集まった四人。運命的な出会いをしたわけでもなんでもない。スーパーカーの結成としては、100点である。
青森の楽器屋がきっかけで集まった4人は、1997年「cream soda」というシングルでデビューする。
97年は、スーパーカーの他に、くるりやナンバーガール、中村一義のデビューした年でもある。「97年の世代」と呼ばれた彼らは、後に日本の音楽シーンに多大な影響を残すことになる。もう大好きなバンドばかり。
そんな「cream soda」が収録されたアルバム『スリーアウトチェンジ』
初期の楽曲はまさに「ザ・バンドサウンド」。ツインボーカルの織りなすクールでアンニュイな音楽が、疾走感とともに押し寄せる。
この感覚が不思議なのだ。この独特な「スーパーカーサウンド」を構成しているのは何なのか。分からないけど、不思議と心地良いのである。不思議なくらい「普通」の四人が集まると、独特な雰囲気が生まれる。ここにスーパーカー最大の魅力がある。
歌声が良いとか、ギターがうまいとか、「特筆」できない。しかし4人の生み出す化学反応は、どんな「特筆」すべき点よりも、個性が滲み出ている。まさしくそれこそ、唯一無二の「スーパーカー」なのだ。

『スリーアウトチェンジ』(SUPERCAR)
そんなこんなで、一気にロックスター街道を走っていく彼ら。青森の楽器屋からトントン拍子である。マンガかよ!
2000年代に入ると、電子音楽を取り入れたり、アンビエントな雰囲気に傾倒する。少し複雑な音楽にはなったものの、しっかり「スーパーカー」なのだ。ここがまたすごいところ。
そんな2002年、最高傑作とも言われるアルバムがリリースされる。それが『HIGHVISION』である。
とにかくふわふわと漂うようなサウンド。何かから解き放たれたような開放感。ずっと聴いていても疲れないアルバムになっている。
正直『スリーアウトチェンジ』のほうが好みだ。でも、初めて『HIGHVISION』を聴いたときの衝撃は凄まじかった。電子音楽って、こんなにも日常にピッタリとハマる瞬間があるのかとビックリしたものだ。
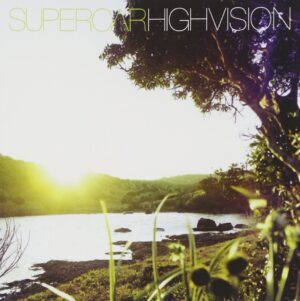
『HIGHVISION』(SUPERCAR)
歩いている風景、電車の車窓から見える景色、それらが少しキラキラ光って見える。
そんなアルバムである。
それは「普通」な4人だからこそ表現できた世界なのではないだろうか。
[ライタープロフィール]
コバン・ミヤガワ
1995年宮崎県生まれ。大学卒業後、イラストレーターとして活動中。趣味は音楽、映画、写真。
Twitter: @koban_miyagawa
HP: https://www.koban-miyagawa.com/

