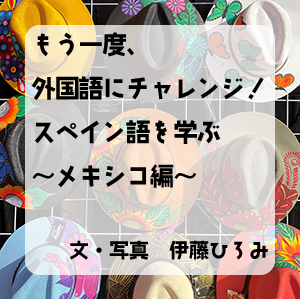第11回 メキシコ、銀街道をゆく
文・写真 伊藤ひろみ
「外国語学習に年齢制限はない!」「ないのではないか?」いや、「ないと信じたい!」
そんな複雑な思いを抱えながら、まずは都内でスペイン語学習をスタートさせた。そして2023年2月、約1カ月間の語学留学を決行した。目指すはメキシコ・グアナフアト。コロナ禍を経て、満を持しての渡航となった。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
<第11回> メキシコ、銀街道をゆく
かつての繁栄はどこへ?
グアナフアト大学語学センターで出会った友人のひとりから、グアナフアト市内に銀の採掘場が残っているという情報を得た。
実は、今回の旅のテーマのひとつが、銀とグアナフアトとの関わり。それがこの町に何をもたらしたのか。歴史にどう影響したのか。スペイン語を学びながら、その答えを探し続けていた。
思わず、その情報に食いつく私。「何、何? それって、どこにあるの?」

グアナフアト市北部に残る銀鉱山跡。廃坑となり、市内を一望できる場所のひとつ
それらしい建物が、ピピラの丘から見えたという。彼は私にスマホで撮った写真を見せながら、説明してくれた。市内を一望できる一枚に、ほんのわずかだが黒い建物が写っている。ピピラの丘の向かい側、山の中腹あたり。「これが銀の採掘場なの? 先日、私がピピラの丘まで行ったときは、まったく気づかなかったのに!」
とある日の午後、気になる場所へと向かった。語学センター横の坂道を北へ歩く。息を整えながら、ゆっくりゆっくり。そもそもグアナフアトは標高約2,000mの高地である。そのうえ、急な登り坂となると、心臓への負担が大きい。さらに石畳の道が多く、すべりやすく歩きにくいため、慎重にならざるを得ない。つんのめったり、ころんだりして、病院のお世話にならないようにしなければ! そう言い聞かせながら。
小1時間くらい歩いただろうか。じんわりと汗がにじむ。しばらくすると、廃墟のように残っている建物があった。入りたかったが、門は固く閉ざされていた。わずかな隙間から中をのぞいてみる。正面にはORIGEN MINERO(鉱山の起源)と書かれた案内看板があるのが見えたが、門の外からは文字が小さくて読めない。さらに、壁面には、採掘していたころの古い写真が飾られている。確かにこのあたりは、銀の採掘場だったところのようだ。係の人でもいればと周りを見渡すが、誰もいない。

門の隙間から撮影した採掘場の一部。当時の様子を示す写真が数点見えたが中には入れず
そのすぐ横の広場には、銀の採掘に使ったと思われる機材やトロッコなどが、無造作に置かれている。陽はあたたかく、まぶしく、木々の影をくっきりと描いている。かすかに風の音だけが耳に響く。眼下に広がる美しいグアナフアトの景色をながめながら、ここが採掘場としてにぎわっていたころを想像してみる。だが、今の姿から、その像を結ぶことはできなかった。
ここはMirador de Rayas(ラジャス展望台)と呼ばれている。落ち着いた雰囲気に包まれ、市内を一望するにはもってこいの場所。Rayasはここの所有者だった人の名前のようである。
銀鉱山跡を探しにヴァレンシアーナへ
週末、ヴァレンシアーナ(Valenciana)へ向かった。銀の採掘場があると聞いたからだ。グアナフアトから北へ約5キロの場所にある小さな町(というより村といったほうがいいかもしれない)。現在廃坑になっているが、かつての銀鉱山の一部を見学できるという。
アロンディガ広場の前からヴァレンシアーナ行きのバスに乗る。20分ほどで到着。広場前のヴァレンシアーナ教会の横の通りから、そのひとつ、サン・ラモン(San Ramon)へ。入場料は50ペソ(取材当時・約370円)だった。

サン・ラモン入口付近。教会からさらに北へ歩き、徒歩5分ほどのところにある
チケットを手に敷地内へ入り、坑口へと進む。案内してくれたおじさんが、ヘルメットをかぶるようにと指示をした。ここからは坑道に沿って、狭い階段を伝い、地下へと潜っていく。照明もついてはいるが、中は薄暗い。気をつけて歩かなければ!
深く進んでいくにつれ、なんだか息苦しくなってきた。かつて、外から空気が入るのは、入口近くにある高い塔のようなところからの一か所だけだったと説明を聞いたからだろうか。暗いし、狭いし、閉所恐怖症の人は避けたほうが賢明かもしれない。
現在、坑道の一部は観光客が見学するために整備されているが、ここを堀り進んでいくのは、大変な重労働である。さらに、危険と背中合わせ。健康被害も深刻だったと思われる。銀が眠っているとはいえ、それを手に入れるために払う犠牲は少なくなかっただろう。
坑道途中、幼いイエスを抱いた聖母マリアが描かれた絵画が飾られていた。こんなところに? いや、こんなところだからこそ、マリアやイエスが必要だったのかもしれない。

坑道内。小窓の奥に聖母マリアとイエスの絵が飾られていた
坑道の入口に戻り、ほっとひと息つく。かつての採掘の様子を示す写真なども展示されている。
敷地内の中央広場では、これからウエディングパーティが行われるようで、従業員はその準備に忙しそうだ。白いテーブルクロスが敷かれ、プレートやカトラリー、かわいらしくアレンジされたブーケなどがセッテイングされている。
かつての過酷な労働現場は、平和で幸福を描き出す場所へと大きな変化をとげていた。

中庭で催されるウエディングパーティ。坑道口は左奥
リアルな人形にぎょっとする
ヴァレンシアーナ教会のそばに、もうひとつ別の見学場所があった。入口には、Mina San Cayetano(サン・カエタノ鉱山)と書かれている。先に訪ねたサン・ラモンの観光客は少なかったが、ここは列をなしていた。入場料は同額だったけれど、何が違うのかな?
10~15人くらいをひとグループとし、それぞれにガイドがつく。まず展示室に案内された。採掘現場に入る前に、ここで説明を受けたり、全体構造を示すジオラマを確認したりして、予備知識を仕入れる。説明はスペイン語オンリーなので、私には猫に小判だったが。
ガイドのあとに続き、いよいよ坑道へ入る。長い階段を下り、どんどん地下深くへ。途中、掘削する坑夫像が置かれていて、ぎょっとする。掘り起こしている様子や、ショートパンツ1枚で、背中に大きな袋を背負っている姿など、妙にリアルな人形。こういうのは苦手だな。わかりやすく伝えるために置いたのだろうけど。

坑道口付近。一列になって階段を下りる
背が低い私でさえ頭がつっかえそうになるところもあり、足元だけでなく、頭上も要注意。サン・ラモンと同様、坑内は暗い、狭い、危ない。どんなに頑強な男性でも、ここで長年働くことはできなかっただろう。
先に入場した展示室の壁面や、坑道口には、当時のヴァレンシアーナの町や銀鉱山での掘削の様子を語る写真が幾枚も展示されている。

過酷な労働現場だったことがわかる資料の数々
ヴァレンシアーナ教会の挙式で幸せになれる?
ヴァレンシアーナ教会のすぐ近くに、ヴァレンシアーナ伯爵の館があると聞き、訪ねてみた。かつては公開されていたが、いつのまにか見学できなくなってしまったようだ。この地を支配した有力者だけに、その影響力の片鱗を見てみたかったが、外観を写真に収めるにとどまった。

ヴァレンシアーナ伯爵の館(左手前)。メイン通り沿いにある
ヴァレンシアーナ教会もまた、ウルトラバロック、チュリゲラ様式の絢爛豪華な建造物のひとつである(第10回のラ・コンパニーア教会参照)。まずは、誰もが正面ファザードに圧倒されるだろう。さらに、中央祭壇も超デコラティブ。ふんだんに金を用いた超絶技巧で人々を驚かせる。

チュリゲラ様式のヴァレンシアーナ教会。青空に薄いピンクのコントラストが印象的
その姿に見とれながら、教会の写真を撮っていたときだった。ドレス姿の女性たちが姿を現した。続いて正装姿の男性たち。これからここで結婚式が行われるようである。関係者以外、堂内には入れないが、せっかくなので、入口近くでその様子を拝見することにする。白いウエディング姿の花嫁が、父親に手をひかれて入って来た。教会関係者もスタンバイOK。聖歌とともに儀式が始まった。
おごそかな雰囲気の中でセレモニーが進行する。ここで式を挙げれば、硬い絆で結ばれるかな。幸せになれるかな。

きらびやかな中央祭壇の前で行われていた婚礼の儀式
スペインとメキシコ、銀鉱山、植民地都市
1546年、メキシコ中央高原地帯、サカテカスで最初の銀鉱山が発見された。その数年後、グアナフアトでも同様のことが起こる。この町の歴史が大きく動いたのは、このころから。ヴァレンシアーナが活況を呈したのは、18世紀半ば。1週間に40トンとも50トンとも言われる鉱石を採掘し、この小さな町に6000人以上の人々が住んでいたという。
サカテカスからメキシコシティへと至る道は、銀の道、銀街道とも呼ばれ、銀の採掘とともに植民地都市が形成され、発展していった。かつての銀の採掘場は、現在そのほとんどが廃坑となっているようだ。すでに採りつくしてしまったからだろう。
銀鉱脈を発見し、その価値づけをしたのは、まぎれもなく、ここに入植したスペイン人たちである。一方、掘削のために労働を強いられたのは、主にそれまでここに暮らしていた先住民、労働力として連れて来られた奴隷たち。富は彼らを素通りし、その多くは本国スペインへもたらされた。だがそれも、スペインが負った他国への借金返済などに流れたとも言われている。
メキシコに限らず、また銀鉱山だけでなく、鉱山資源などの発見により、その地が急変する。トレジャーハンティングはロマンともいえるが、大きな危険も孕んでいる。
スペイン語の表記と発音
スペイン語で書かれた文字や文を見て、最初に「おや?」と思うことのひとつが、疑問符や感嘆符。英語的感覚からすると、文末に置くのは理解できるが、スペイン語ではそれらを文頭にもつける。しかもさかさまにして。この表記のルールはスペイン語独特のものである。最初は違和感があるかもしれないが、慣れてくると文の機能がわかりやすく、便利な方法だと感じるだろう。たとえば、こんなふうに。
¿Qué tal? 元気?/ケ・タル
¡Hola! やあ!/オラ
もうひとつ、表記上で大事なことは、単語によってアクセント符号(スペイン語ではacento アセント)をつけるということ(ついていない語は、2か3のルールを適用)。スペイン語には厳密なアクセントのルールが存在する。
<アクセント位置の規則>
- アクセント符号がある語→アクセント符号の位置
(例)Japón の場合、oにアクセント(日本/ハポン)
2.母音またはn、sで終わる語→後ろから2つめの音節
(例)amigoの場合、iにアクセント(男性の友達/アミーゴ)
3. n、s以外の子音字で終わる語→最後の音節
(例)hotelの場合、eにアクセント(ホテル/オテル)
最初はうっかり書き忘れがちだが、単語を覚えるときに、どこにアクセントがあるかをよく確認する必要がある。また発音上も、アクセントがある部分を強く(やや長く)発音しなければならない。これが私にはなかなか難しく、しょっちゅう先生に指摘されている。
文字が小さかったりすると、アクセント符号を見逃すこともあるので要注意。しっかりチェックできるよい目をもっているならともかく、老眼にはつらい! やっぱり若いうちに始めるべきだったかな?
[ライタープロフィール]
伊藤ひろみ
ライター・編集者。出版社での編集者勤務を経てフリーに。航空会社の機内誌、フリーペーパーなどに紀行文やエッセイを寄稿。主な著書に『マルタ 地中海楽園ガイド』(彩流社)、『釜山 今と昔を歩く旅』(新幹社)などがある。日本旅行作家協会会員。