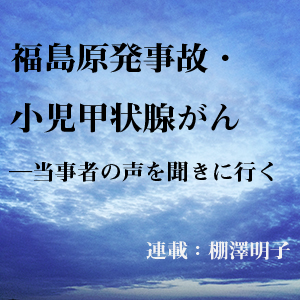第6回 「やっぱり、因果関係について知りたいっていう思いが強かったんです。…理由は必ずあるはずなのに、わからないっていうことで終われるわけないでしょう」
――ふゆきさんのケース(後半)
棚澤 明子
一人きりで臨んだ手術
2021年、新型コロナウイルスが蔓延し、面会が完全に不可能ななか、ふゆきさんは甲状腺がんの手術を受けた。
当日、病院に向かったのも一人だ。
事前の打ち合わせで、病院側から「手術が終わって、ベッドに横たわったまま病室へ運ばれる廊下でなら家族に会える」と言われたが、ふゆきさんは断った。
そのときの気持ちを表す言葉を、ふゆきさんは注意深く探る。
「べつに来なくてもいいよ、一人で大丈夫だからって私から家族に言ったんです。病室でゆっくり話せるならともかく、そんな、話もできないような状態のところに来てもらうのが、すっごく嫌だったんですよね。申し訳ないっていうことではなくて、わざわざそんなことのために来てもらいたくなくて。両親も、わかったわかったっていう感じで、病院には来ませんでした」
手術直前も、緊張や恐怖心で震えるようなことは一切なかった。記憶に残っているのは、直前の身支度に手間取ったことだ。
「水色の手術着を着るのですが、当時、髪の毛が長かったので、うまく帽子に入らなくて。入れても入れても出てきちゃうんですよ。それで、イライラしました。あと、私がなで肩だからかもしれないのですが、手術着の肩のところも全然とまらない。それにもまたイライラしましたね。看護師さんがガムテープを持ってきて貼ってくれたのですが、それでもとまらなくて。看護師さんが「私が押さえておくんで、とりあえず行きましょう!」って手術着を押さえてくれて、そのまま手術室に入りました」
感情云々の話ではなく、がんを治すために手術は避けて通れないもの。それだけのことであって、記憶に残っていることはとくにない。そんな話の流れのなかで、手術着の水色は強烈な印象として残った。
2時間ほどの手術で、ふゆきさんは右の甲状腺を切除した。
看護師に「終わりましたよ」とポンポンと肩口をたたかれた記憶があるという。家族と会うこともできると言われた廊下を、麻酔もさめやらぬ状態で管につながれたまま運ばれていく。
「今思えば、やっぱり家族に見られなくてよかったなと思うんです。ちょっと説明するのが難しいんですけど……。私のなかでは『わざわざ、顔を見るためだけに来てもらうのは申し訳ない』ではなくて、『見られたくない』という方が近いかな。当時は、単純に一人で大丈夫だという意味で、来なくていいと言ったのですが、親にとっては元気だけが取り柄の娘ががんになって、手術もしなくちゃいけなくなったわけで。いざ手術しましたっていうときに、その姿を見られたいかって言うと、やっぱり見られたくなかったんだなって……」
「治療を受けて、1日でも早くラクになる」という明確な目的のために、目の前の現実を受け入れ、すべきことを着々とこなしてきたふゆきさん。
告知の話にも手術の話にも、「つらい」という言葉を一切使わなかった彼女が、「本当につらかった」と振り返ったのが術後のことだ。
術後24時間は、足を曲げたり、手首を動かしたりする以外は、体を動かしてはいけないという指示が出た。傷口は医療用ボンドで止めてあるだけなので、首を勢いよく動かしてしまったら、傷口が開いて出血する恐れがあるというのだ。「首を動かせないというのが、あれほどつらいとは……」とふゆきさんは振り返る。しばらくたって、首を動かす許可が出た後も傷口が開くことが怖くて動かせず、偏頭痛まで出てきてしまった。
退院は約1週間後。支払いも兼ねて迎えにきてくれた父親と2人で、病院の近くにあったコメダ珈琲に入って昼食をとった。「久しぶりのまともなごはん」だったビーフシチューとクリームオーレを、ふゆきさんは平らげたという。
首の傷口が開いたらどうしよう……
退院してからも、「首を動かしたら傷口が開くのではないか」という不安にとらわれ、常に首に力が入り、わずかな物音でさえ頭に響くようになってしまったという。開放的な気持ちにはなかなかなれず、ふゆきさんは、どんどん不安定になっていく。
手術はちょうど大学を卒業した年だったのだが、とても就職のことを考える気にはなれない。もちろん、絵に集中することもできない。自分の体以外のことを考える余裕をまったくもてないまま、時間が流れていった。
「私は、もともと物事を悪い方に考えがちだし、口も悪いんです。それは自覚していたのですが、こんなにひどい人間だったかな? と思うくらいネガティブ思考になってしまったり、自分でも『こんなこと言う?』と思うような発言が、止まらなくなってしまったり……。まわりに悪口を言われているように感じてしまうこともありました。これまでだったら、『悪い方向にばっかり考えていたら、自分のためにならないから』って切り替えることができていたんです。でも、退院後は、なぜかそれすらできなくなってしまいました」
手術の傷痕に貼らなければならない腫れ止めのテープを貼りかえるのも苦労した。
最初の頃は母に剥がしてもらっていたが、剥がすときには痛みを伴うし、慣れないので30分以上かかることもある。
「母に『早くしてよ!』と怒鳴ったこともありました。家族みんなから『そんなに怒らなくても……』と言われのだけれど、どうしても冷静になることができなくて、『うるさい!黙ってて!』と怒鳴ってしまう。家族は気をつかってくれていたけれど、あの時期は家族ですら敵に見えたりして、本当に不安定でしたね……」
医師からは、この先10年にわたって、甲状腺ホルモン剤であるチラージンを飲み続けるようにと言われている。1日飲み忘れた程度では大丈夫だけれど、1〜2週間飲み忘れれば影響が出るし、1日に2日分飲むのもいけない。その人にとっての適量を保ち続けなければ、心身両方に影響が出てしまうという。そもそも薬を飲むことが嫌いだというふゆきさんにとっては、つらい義務が課されることになった。
がんと原発事故の因果関係を知りたい
そんなある日、父親がつながりのある弁護士を通して、「甲状腺がんを患っている福島の若者たち6人が東電を提訴した」という話を聞いてきた。
ふゆきさんは、それまで自分のがんと原発事故の因果関係について、深く考えてきたわけではない。福島県から甲状腺がんの子どもがたくさん見つかっていることは知っていたが、その問題と自分のがんが直結するのかどうかは、確証がないままだ。そもそも、原発事故の問題には全然触れてこなかったから情報もないし、どこから調べていいのかもわからない。
そんな状態だったけれど、裁判のことを詳しく知りたいと思い、父親を通して弁護士と連絡をとってもらうことにした。
「ただ、私は裁判というものにずっと嫌悪感を抱いていたんですよ。裁判が起きるっていうのは、罪を犯しておきながら、自分は悪くないって主張している人に、膨大な時間をかけて『あなたが間違っているんですよ』ってわからせていく、ということですよね。自分の時間をないがしろにしてまで、反省もしないような人を相手に闘う意味があるのかなって。自分が被害者の立場に立ったことがなかったから、そう感じていたのでしょうね」
因果関係についての確証はなく、裁判というものには嫌悪感がある。それでも、ふゆきさんは原告団に加わる決意をした。
「やっぱり、因果関係について知りたいっていう思いが強かったんです。なぜ、4回の検査で一度も異常がなかったのに、5回目の検査で突然がんが見つかって、しかもそれが手術をしなければならないような大きさになってしまっていたのか? これは被ばくの影響なのかどうなのか? 理由は必ずあるはずなのに、わからないっていうことで終われるわけないでしょうっていう気持ちですね。裁判に参加すれば、この問題の近くにいられる。近くにいれば、因果関係についてわかることもあるかもしれない。迷いはありませんでした」
訴訟に参加し、原告数人で顔を合わせる機会はあったが、6人全員と顔を合わせる機会はないままだった。みな、それぞれ仕事や勉強に忙しく、住まいも離れているので、日程を合わせるのが難しかったのだ。
「わがままかなと思ったけれど、私から皆さんに『すいませんけど、1回全員で集まれませんか?』って声をかけました。正直、1回も会っていない原告さんと『一緒にがんばりましょう!』っていう気持ちになるのは難しくて。一緒に闘ってためには、どうしても一度会っておきたかったんです。裁判に参加してしばらくして、やっと全員と顔合わせができました。どんな人たちだったのかというと……そこらへんの若い人たちっていうとあれだけど、自分と変わらない日常を送っている普通の同世代の人たち、でしたね」
6人のことを形容するのにふゆきさんが使った「そこらへんの人たち」という言葉は、後々まで私のなかに残った。
決して特別な人たちが原告なのではない。普通に生きてきた普通の若者たちの身にこうしたことが起こっている。それがこの問題なのだ。
「私は、自分の病気のことを家族以外の人には誰にも話していなかったんです。友だちにも話す気になれなくて。体験したことのない人たちに向けて話したところで、何が変わるんだろうっていう思いもありましたから。でも、この6人には、今の状況を普通に話せました。みんな似たような体験をしているからかな。そういう意味では、会えてよかったなって思いました」
闘うのは、簡単なことではない
支援者である大人たちは、おそらく、ふゆきさんに次いで8人目、9人目、と声をあげる若者が現れることを待っているのだと思う。
でも、ふゆきさんに続いて追加提訴した人は、今のところいない。原告団は7名のままだ。
「正直、追加提訴は私だけだろうっていうのは想定していました。闘おうっていう気持ちにはなかなかなれないと思うんですよね。やっぱり、こうして活動することで、何かの拍子に自分の身元がバレるんじゃないか……と思うと怖いですから。ただ、私は身元がバレる危険性があるとしても、やっぱり因果関係を知りたいと思ったんです。因果関係をはっきさせることで、300人以上もいる甲状腺がんの若者たちの手助けになれるんだったら闘いますっていう気持ちです。もちろん、この気持ちを同じ立場の若者たちに押しつけるつもりはありません。差別とか誹謗中傷をされたい人なんか、いるわけないですしね。声をあげないからって、弱い人間だとも思いません。裁判に参加した以上、途中でやめるのは言語道断だから、何があっても最後までやり通すっていう覚悟がないとできないですしね。闘うっていうのは、簡単なことじゃないと思うんです」
「身元がバレるのは怖い」という声は、原告全員に共通している。
原発事故後、その影響を調べるための公的な検査でがんが発覚する。その事実に直面して、事故とがんの因果関係を明らかにしてほしいと思うのは当然のことだ。患者側が徹底して身元を隠さなければならない社会には、大きな歪みがあるとしか思えない。
「やっぱり“被ばく”ということについて、差別的なことを言う人たちもいますよね。福島=原発っていうイメージをもっている人はまだたくさんいるし、その上で差別的なことを言う人たちもいます。私自身、現時点で攻撃的なことを言われたことはないけれど、でも、「おもしろければいい」みたいな考えで他人を叩く人はいますよね。私は、そんな人たちに負けている暇はないっていうのかな。何の信念もない人たちに誹謗中傷される筋合いはないと思うんです。そういう人たちは、私たちの話をしっかり聞いていないだろうし、触れてもいないだろうし。もし、自分の家族とか愛する人が同じようにがんになったら……ということも考えられないような人たちに、どうして私たちが苦しめられないといけないのか、という気持ちはありますね」
裁判官の皆さん、私の名前はわかりますか?
法廷での意見陳述は、2023年1月25日に終わった。陳述書は、裁判官への語りかけで締めくくられている。
「裁判官のみなさん。
私たちは今、匿名で戦っていますが、一人ひとり名前があります。
私の名前はわかりますか。
かつての私のように、裁判官の皆さんにとっては、ひとごとかもしれません。
私がそうだったから、痛いほどわかります。
でも、私たちがなぜこのように立たざるを得なかったのか。
それだけでも理解してほしいです」
こうした言葉が出てきた背景には、原告一人ひとりがじっくりと意見陳述をすることに対して裁判官が否定的である、という状況があった。実際、裁判が始まった当初は、原告全員が意見陳述できる見通しが立っておらず、「原告全員に意見陳述をさせてください」という署名活動が行われ、6,395筆が集まっている(その後、全員の意見陳述が実現することとなり、2023年3月15日に7人目の意見陳述が終了している)。ふゆきさんは、当事者を蔑ろにしてスピードや効率を求める裁判官の姿勢が許せなかったのだ。
多感な年齢である原告たちが、つらい過去を掘り返しながら意見陳述書を書き上げるには長い時間がかかる。また、意見陳述当日も、ふゆきさん自身がそうだったように、話しながらさまざまなことを思い出して言葉に詰まってしまったり、泣いてしまったりして時間がかかることもある。でも、それは自らの体が病に冒された若者たちにとって、当然のことだ。そして、原告にとっては自分の身に起きたことをじっくりと言語化することが、それ以外の立場の人にとってはその言葉を真摯に受けとめることが、この裁判では非常に重要になる。
「裁判官は、『ほかに300人以上も苦しんでいる人たちがいるのだから、その人たちのためにも、早く裁判を終わらせてこの問題を解決すべきだろう』とも言いました。言っていることはわかりますよ。でも、私は気にくわないです。10年以上ほったらかしにしてきたものを、たかが数年で終わらせるつもりなんでしょうか。だから、『あなたがたにも名前があるように、私たちにも名前があるんですよ、覚えてくださってますか?』っていう言葉を投げかけたかったんです。陳述しているとき、裁判官と目が合いました。どうせ、ずっと下を向いているんだろうなと思っていたのですが、ああ、この人たち、見てくれてはいるんだなって。こっちを向いて、話を聞いてはいるんだなって思いましたね」
この裁判に関して、ネットに「気持ちはわかるけど、過去のことなのだから、前を向いて進むべき」と書き込んでいる人がいるのを見て、ふゆきさんは反発を感じたという。
「原発事故のことは忘れてはいけないし、なかったことにはしてはならないと思います。そうしなければ、また同じことを繰り返しますから。確かに過去に起きたことだけれど、未来に繋げていかないといけないと思うんです」
なかったことにしないためにも、自分の身に起きたことを伝えたい。応援してくれている人にも、しれくれていない人にも、立場を問わず、みんなに話を聞いてほしい。
今、ふゆきさんの思いは、そこに集約されている。
「今まであなたが見てきたものがすべてじゃないんですよ、ということを伝えたい。私自身が『自分は関係ない』と思っていた人間なんで、当事者ではない人たちの気持ちもわかるんです。でも、ちょっと状況が違ったら、私とあなたは逆の立場だったかもしれない。あなたがここに立っていたのかもしれない。だから、どういう立場の人たちに対しても、『自分は関係ない』っていう考え方はありえない、ということを伝えたいと思っています。100%わかってもらうのは無謀なことかもしれない。でも、何回でも聞いてほしいんです。何回も何回も聞くことで、伝わるっていうこともあると思うから。それぞれの立場で言いたいことはあるかもしれないけれど、でも、まずは私たちの話を聞いてほしいって、すごく強く思っています」
ふゆきさんは、数カ月前に新しい仕事に就いた。
まだまだ覚えなければならないこともたくさんあり、余裕はない。一方で、病気のことを考えると、湧き上がってくるのは不安ばかりだ。
でも……とふゆきさんは言う。
「不安を抱いたところで、自分が苦しいだけなんですよね。大事なのは、今できること、今すべきことをしっかりやっていくことだと思っています」
その言葉は、受けとめ切れないほどの思いを抱えながらも、告知や手術に一人で立ち向かってきた姿そのものだった。
[ライタープロフィール]
棚澤明子
フリーライター。原発や環境、教育、食など、社会課題を主なテーマに執筆。著書は『福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を』『福島のお母さん、いま、希望は見えますか?』『いま、教育どうする?』(弘田陽介氏との共著)(すべて彩流社)ほか。16歳、19歳の男の子の母親。