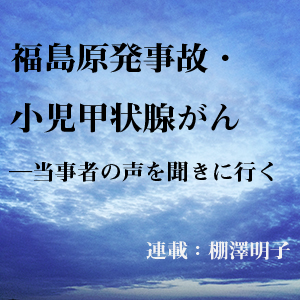第4回 「他に誰もいないのであれば、私はひとりでも闘うつもりだったんです」
――鈴木ちひろさんのケース(後半)
棚澤 明子
これで終われる! これですっきりする!
大学3年生だった2016年夏、ちひろさんは1週間ほど入院し、甲状腺の片葉を切除する内視鏡手術を受けた。たまたま執刀医の予定が空いていたのが前期テストの最終日だったので、テストを終えてその足で病院へ。大学を休学せずに済んだことが不幸中の幸いだった。
「手術の前は、これでもう終われるんだ、これでもうすっきりするんだって、ちょっとウキウキするような気持ちでしたね。先生が手術の内容をきちんと説明してくれた上に、『絶対、大丈夫だから!』って言ってくれたことも、すごく心強かったです。生まれて初めて入った手術室は内視鏡の設備がすごく先進的で、なんだかドラマのなかみたいだなあって」
きっと大丈夫。そう思って臨んだ手術は確かに順調で、2時間の予定が1時間少しで終わった。幸い、転移もなかった。
ただ、麻酔が体に合わなかった。目覚めてから何度も吐いたり、低体温で震えが止まらなくなったりして、予想以上に苦しい思いをしたという。
それでも、心のなかには「これで終わったんだ」という喜びが満ちた。
左右両葉の甲状腺を切除すると甲状腺ホルモンを自力でつくり出せなくなるため、生涯にわたってホルモン剤を飲まなければならなくなるが、ちひろさんは片葉しか取らなかったため、いまはホルモン剤を飲む必要がないという。
内視鏡手術だったので傷跡は小さく、術後もすぐに普通食が出た。飲み込むために苦労することもなかったという。
事故当時から放射能の危険性を気にかけて「ちひろだけは外に出ないで」と言い続け、手元を離れてからも「早く2巡目の検査を受けるように」とたびたび電話をくれた母は、仕事を休んで1週間つきっきりでそばにいてくれた。ただ、心労が重なったせいか、途中で体調を崩し、入院生活の後半はちひろさんのベッドで横になっていたという。
術後は免疫力が低下するために風邪をひきやすくなると言われたが、ちひろさんも例に漏れず、その後はなかなか体調が安定しなかった。月に1〜2回は風邪をひく。ホルモンの数値もだんだんと低下していき、一時期はホルモン剤も飲まなければならなくなった。2019年には体調が一気に悪化して、肺炎と喘息と気管支炎、すべてに罹ってしまったという。
当時は東京の広告代理店勤務。「やりたい仕事だった」と言うが、広告代理店といえばハードワークの代名詞だ。結局は、体調不良で続けることができなくなってしまった。
忙しい仕事だと体調を崩してしまうかもしれない……。その不安は大きく、現在はマイペースで働ける事務の仕事に就いている。
こうして、体調は落ち着きを取り戻していったが、
「見つかるのがあと少し遅かったら、私は死んでいたと思います」
と、ちひろさんは言い切っている。発見されたときの腫瘍は5mmだったが、気管のそばにあったので、大きくなれば気管に付いて全身にまわってしまいかねなかったのだ。そして、その腫瘍は発見から手術までの1年間で、倍の大きさになってしまっていた。
それでも、福島の小児甲状腺がんについては「スクリーニング効果だ」「過剰診断でしかない」という声が根強い。「そのまま放置しておいても寿命をまっとうできるようながんまで一斉検査で見つけて、処置しているだけだ」という論だ。このような論に対しては、福島県立医大で執刀を一手に引き受けてきた鈴木眞一医師も「自分が手がけた手術のなかに、不要だったものなど1件もない」と明言している。
2019年9月には「県民健康調査は、生涯にわたって健康には影響しない潜在がんを見つけているだけで過剰診断につながる。県民の不安を煽るデメリットしかない。検査そのものを縮小すべきだ」という声が福島県の小児科医会からあがり、大きな議論になった。こうした声に対しても、ちひろさんは不信感を募らせている。
「検査を受けて大丈夫だって分かることで安心して暮らせるんですよ。普通の健康診断だってそうですよね? それを“デメリット”だと言う姿勢は、ちょっとおかしいと思うんです。なかったことにしたいとしか思えません」
「過剰診断だから騒ぐことはない」という声も「検査は縮小すべきだ」という声も、まったく理解できない、とちひろさんはため息をつく。
訴訟を起こすなら、身元を隠さなければ
もともと原発に関する知識は何もなかったというが、事故後は家族がニュースを見ながら交わす言葉を聞きながら知識を蓄えた。
「うちは、おじいちゃんがいつもNHKをつけていて、それを見ながら家族がめいめい好きなことを言うようなフランクな雰囲気がありました。放射能のことも、みんなざっくばらんに話していたんです。そこで知らない言葉が飛び交っていると、スマホで調べたりして。そんな環境だったから、私は社会のことや政治のことを考える習慣がついたのでしょうね」
強烈に記憶しているのは、2013年、オリンピック誘致のために安倍元首相が「福島はアンダーコントロールだ」という演説をしたことだ。どうして、何も分からないのに、そんなことが断言できるのだろうか。
告知の際、医師が唐突に「原発事故との因果関係はありません」と言ったこと。甲状腺がん患者を対象にした県民健康サポートを受けた際、保健師が「甲状腺がんと原発事故の因果関係はないけれど、がんになった人を支える事業を非公開で行っている」と言ったこと。どうして、まだ何も調べ切っていないのに、誰もが「因果関係はない」と断言したがるのか?
そうした不信感が「原発事故と甲状腺がんの因果関係をはっきりさせたい」という思いにつながってく。
「本来100万人に1〜2人だという小児甲状腺がんが、38万人の検査で100人、200人……と見つかっているんですよ。いまはもう、300人を超えていますね。何もないわけがないと思うんです」
国への不信感は、やがて「法廷で因果関係をはっきりさせたい」という思いに発展した。
学費だけでも大きいのに、さらに医療費で両親に負担をかけてしまったことへの申し訳なさも大きかった。というのも、ちひろさんが手術を受けた当時、内視鏡手術は県民健康サポートの対象外だったので、手術は自費だったのだ。
因果関係を明らかにして賠償金を受け取ること、そしてすべての小児甲状腺がん患者が生涯にわたってサポートを受けられるようにすること。
これらを、なんとかして実現させたい。
とはいえ、当時はまだ大学生。資金も用意できないし、そもそも誰に頼めばいいのかも分からない。ただ、両親は最初から肯定的だった。「裁判をサポートしてくれるような団体があったら、お願いしてみたいな」とつぶやいたところ、「やりたいなら、やってもいいんだよ」と返してくれたのだ。
実際、ちひろさんが動いたのは、社会人2年目のときだ。訴訟に踏み切った直接のきっかけは、時効が気になったこと。時効は損害を受けたときから10年後だと言われるが、原発事故から10年なのか、がんの告知から10年なのかが分からなかった。もし事故から10年だったら、間に合わなくなるかもしれない。その焦りが背中を押した。
ちひろさんは、知人を通して弁護士に「訴訟を起こしたい」という意志を伝えた。驚いたのは、その弁護士から「同じように考えている若者がほかにもいる」という返事がきたことだ。
「この10年間、自分と同じような気持ちを抱えている若者はいないと思っていたんです。当事者同士の交流は一切なかったし、家族の会に顔を出すのは保護者ばかり。訴訟を視野に入れているという親御さんに会ったことはあるけれど、子ども本人は『これ以上がんの話には触れないでほしい』とか、『できることなら忘れたい』という人の方が多い印象だったんですよね。だから、私がおかしいのかな、と思っていました。訴訟を考えている当事者がいると知ったときは、とにかく驚きましたね」
「でも、他に誰もいないのであれば、私はひとりでも闘うつもりだったんです」
ちひろさんは、はっきりとそう言い切る。自分のためだけではない。当時すでに300人に迫る勢いで甲状腺がんの若者が増え、そのなかには自分よりずっと年下の子たちもたくさんいたからだ。
「私より症状が深刻な子も、がんになったことで将来を考えられなくなって、精神的に参ってしまった子たちもいると聞いていました。その子たちのためにも早く裁判を起こして、勝訴して、全員がしっかりとサポートを受けられるようにしたいなって。そのためには、すでに大人になっている自分が最初に立ち上がらなくちゃいけないと思ったんです」
訴訟を起こすにあたって大きな懸念事項となったのは、いかに身元を明かさずに闘うのかということだ。
というのも、福島県内には甲状腺がんについて大っぴらに語れない空気がある。つまり、「結果的に被害は出なかった」としたい流れがあるのだ。それは、原発事故によって放出されたセシウム137の半減期は30年であるにもかかわらず、事故から1〜2年後には「観光を誘致しよう」「福島のものを美味しく食べよう」という“安心安全キャンペーン”が張られていたことからも分かる。そこには、「2020年の東京オリンピックまでに避難者をゼロに」というスローガンのもと、避難指示を次々と解除していきたいという国の思惑も多分にあったのだろう。
10年過ぎれば、「もうすっかり安心だ」と思って暮らしている人もたくさんいる。農業や漁業に携わる人たちのなかには、甲状腺がんの話を持ち出されることを、いわゆる「風評被害」だと憤る人もいるだろう。
私も、福島県民である知人に甲状腺がんの現状を尋ねたところ、「その話はタブーだから触れない方がいい。みんなもう終わったものだと思いたいんだから」とたしなめられたことがある。
また、賠償金を求める訴訟がいかに正当な闘いだとしても、妬みの目を向ける人も必ずいる。
ちひろさんは、事故後の故郷を思い出して言う。
「浜通りで被害にあった人たちが、私たちの地域にもたくさん避難してきたんです。その人たち、みんな賠償金をたくさんもらって、大きな家を建てたんですよね。それを見た地元の人たちが『あの人たちは賠償金もらってるから……』って、妬みからけっこうひどいことを言うのを目の当たりにしました。お金が絡むと、人は何を言うのか分からないものなんだなって……」
まだ10代だったちひろさんが見た人間の本性だった。
私自身も、震災後の取材で何度も同じような言葉を聞いた。「被害者が賠償金を受け取るのは当然のことなのに、自分はもらっていないから悔しくて、浜通りからの避難者が建てた新築の家を見るのがつらかった。『賠償金御殿だ』とけなして、溜飲を下げたこともある」と正直な心情を話してくれた人もいる。
「甲状腺がんになったことだけならまだしも、訴訟を起こすことは誰にも言えないですね。やっぱりバッシングの対象になるのは怖いですから。私だけでなく、家族も暮らしていけなくなるかもしれませんし。だから、原告になるっていうことを打ち明けたのは、家族以外には親友ひとりだけです」
被害をなかったことにすることも、被害にあった者同士が叩き合うことも、無意味だと思う。けれども、その気持ちを想像することは難しくない。
多かれ少なかれ、誰もが苦しみを抱え続けているのだ。
提訴
提訴は2022年1月27日。原発事故後、健康被害の責任を住民が東電に問う日本初の裁判となった。提訴時に集まったのは、17〜28歳(事故当時6歳〜16歳)の男女6人。年齢も病状もさまざまでありながら、同じ思いを抱えて立ち上がった同志だ。
第1回口頭弁論は5月27日。
「生まれて初めて裁判所に入って、わあ、こういうふうになってるんだなあって。自分がやりたいやりたいって言ってやっと実現した裁判なのですが、具体的な想像ができていなかったのでしょうね。裁判所に入ってみて初めて、ああ、本当に始まったんだ……って実感しました」
当日は、27席分の傍聴券を求めて227人が並んだ。身元を明かせない原告たちは支援者の前にも姿を見せることができないため、別のルートで法廷に入り、衝立の裏に並ぶ。ちひろさんは、この日の長蛇の列を実際には見ていないが、写真を見せてもらったという。
「批判されることはあっても、応援してくれる人なんていないだろうと思っていたんです。だから、行列の写真を見せてもらったときは、正直、びっくりしました。こんなにたくさんの人が集まってくれたんだ……って」
原告6人全員そろっての交流会が開かれたのは、裁判が始まってからだった。
投票によって、ちひろさんは原告団長に選ばれた。「みんなに教えてあげられることなんて何もないのに、私が選ばれちゃって……」と笑うが、自分より年下だったり、症状が重かったりする原告たちの状況を細かく把握し、自然な気づかいを見せるちひろさんの様子からはリーダーとしてのやさしさと気概が伝わってくる。
初の顔合わせの日は、「一緒にがんばっていこう」と励ましあって安心できたものの、お互いに腹を割って話すまでには至らなかった。
6人の関係が大きく変化したのは、第1回口頭弁論で1人目の原告が意見陳述をしたことがきっかけだった。
告知の際に「手術をしなければ23歳まで生きられない」と言われたこと、再発によって大学を辞めざるを得なかったこと、健康な同年代の友だちに嫉妬してしまうこと……。それを聞いていた原告たちは衝立の裏で泣いた。
「それまで涙を見せたことがなかった子たちも、みんな泣いたんです。そのときにわーっと感情を出したことがきっかけになって、お互いの病気のこととか、苦しい気持ちとか、本音を話せるようになりました。関係性が変わったんですよね。だから、あの日は私にとってすごく大きな意味があるんです」
後で公表されたこの意見陳述書を読んだことによってこの裁判を応援すると決めた人を、私は何人か知っている。魂から絞り出した声は届くべきところに届き、受け取った人たちの行動も関係性も変えるほどの力をもつのだ。
提訴直後の2月、小泉純一郎氏、菅直人氏ら5人の首相経験者がEUの執行機関・欧州委員会の委員長宛てに「多くの子どもたちが甲状腺がんに苦しんでいる」と記した書簡を送ったところ、政府が即座に「そうした誤った情報を広めることは、差別や偏見につながる」と批判した。批判したメンバーのなかには、福島県知事の内堀雅雄氏も含まれている。
このニュースに、ちひろさんは思わず感情的になるほど大きな怒りを覚えたという。
「批判したっていうことは、『苦しんでいる人はいない』と言ったということですよね。甲状腺がんについてはただでさえも語りにくい空気があったけれど、影響力のある人たちのこの発言で、さらに語りにくい空気ができてしまったように感じています。ほかの原告も家族も、みんなダメージを受けていますね……。甲状腺がんの話題に触れたくない現地の人たちにも、そもそも甲状腺がんに罹ってしまった若者たちの存在を知らない人たちにも、まずは現実を知ってほしい。知ってもらうことで、安易な批判が出ないような空気をつくっていきたいんです」
語りにくさやバッシングがある一方で、第2回、第3回の口頭弁論にも傍聴券を求めて長蛇の列ができた。裁判を支援するためのクラウドファンディングには約1700万円が集まり、応援メッセージも2000通近く寄せられている。
これもまた、まぎれもない現実だ。
インタビューの最後に、ちひろさんは応援してくれている人たちへ向けた感謝の言葉を口にしようとした。
「温かい応援メッセージには本当に勇気づけられているし、本当に心強く……」
そこで言葉に詰まり、涙をぬぐう。
インタビューの最中、何度も「応援してくれている人なんていないと思っていた」という言葉が出てきたことを思い返す。謙遜でも何でもなく、ちひろさんは本当に味方なんていないと思っていたのだ。それでも、自分のためだけでなく、たくさんの若者たちのために、たったひとりだとしても闘おうと思って立ち上がったのだ。
改めて、その決意の揺るぎなさを思う。
[ライタープロフィール]
棚澤明子
フリーライター。原発や環境、教育、食など、社会課題を主なテーマに執筆。著書は『福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を』『福島のお母さん、いま、希望は見えますか?』『いま、教育どうする?』(弘田陽介氏との共著)(すべて彩流社)ほか。16歳、19歳の男の子の母親。