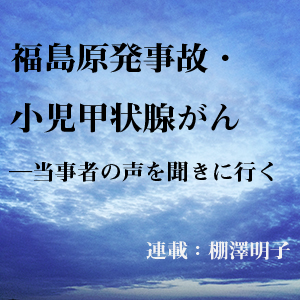第5回 「以前は、どこか他人事だったのかもしれない。甲状腺がんになった子がたくさんいることは知っていたけれど、私自身はがんじゃなかったから」
――ふゆきさんのケース(前半)
棚澤 明子
2022年1月27日に6人の若者が東京電力を提訴したことによって始まった「311子ども甲状腺がん裁判」。そこに7人目の若者が参加した、というニュースを聞いたのは同年9月のことだ。
6人の行動から力を得て立ち上がった若者がいるという事実に、私たち大人も大きな力をもらったように思う。追加提訴という形で遅れて参加するのは、最初の6人とはまた違う勇気が必要だったのではないだろうか。
いつか彼女の言葉を聞いてみたい。そう思うようになった。
その願いが叶ったのは、2023年の春だった。
指定された取材場所に時間より少し早く着くと、7人目の原告であるふゆきさん(仮名・24歳)もちょうど到着したところだった。
「今、駅前の大通りに警察がたくさんいましたよね? 事故か何かでしょうかね?」
インタビューが始まる前、簡単な挨拶を済ませたあと、そんな言葉をかけられた。
いつか話を聞いてみたいと思い続けてきた彼女。徹底的に名前を伏せ、衝立の向こうで証言する存在である彼女。その彼女も、この人の波のなかを自分と同じように歩いてきたのだ、という当たり前の事実にはっとする。
甲状腺がんの問題は、衝立の向こう側にあるのではない。「ここ」にあるのだ。
彼女たちは、「原告」として、「患者」として生きているわけではない。たくさんの苦しみや葛藤を抱えながらも、私たちと同じ人混みのなかで生きている。
「7人目の原告としての意気込みを聞こう」と力んでいた私に、ふゆきさんの何気ないひと言は、「ひとりの若者としての素顔に触れよう」という初心を強烈に思い出させてくれた。
*******
私たち、明日はどうなっちゃうんだろう?
ふゆきさんは、福島県の中通りで生まれ育った。
自分から友だちを誘うようなことはめったになく、誘われない限りは家のなかで遊んでいる“インドア派”の子どもだったという。
「小学生の頃は学校から帰ってきたら宿題やって、ゲームやって、絵を描いて……だったかな。ゲームは3DS。ソフトはもう売っ払っちゃって、タイトルは全然覚えていないけれど、女の子のファッション系のゲームが多かったような……。絵も、女の子を描くのが好きでしたね」
東日本大震災が起きたのは、小学6年生のとき。
音楽室で卒業式の練習をしているときに大きな揺れに襲われた。隅に積み上げてあった木の椅子が大きな音を立てて崩れ、みんながパニックに陥ったという。「校舎にいる生徒はみんな体育館に集まるように」と言われて行った体育館の床は、天井から落ちてきたほこりや木くずで埋め尽くされていた。
「女の子はみんな泣いちゃって、私もつられて泣いちゃいました。そのうち、普段は泣かない男の子たちも『もうダメだー! わーん!』っていう感じで泣き始めて。うちは、父が迎えに来てくれたのですが、用事があって一度戻っちゃったんです。父がまた迎えに来てくれるのを待っているときに、同じマンションの子の親が迎えに来たから、私も一緒に連れて帰ってもらいました。あれは何時だったんだろう、もう真っ暗でしたね」
帰ってはみたものの、自宅は割れた食器が散乱し、とても入れるような状況ではない。困っていたら、近くにあったモデルルームのプレハブが、マンションの子どもたちのために開放されることになった。ふゆきさんは近所の子どもたちと一緒に、そこで1〜2日過ごしたという。
地震の翌日である3月12日15時36分、福島第一原発の1号機が爆発した。
原発からふゆきさんの住まいまでは、50kmをはるかに超える距離がある。未曾有の事態ゆえ、誰にとっても危険性の有無を判断するのは難しかったにちがいない。この地域で子育てをしていた母親たちにインタビューをしたことが何度かあるが、原発との間に距離があるだけに、事故直後の危機感は人によって大きく違ったという印象がある。
「あのときのことは記憶が曖昧なのですが、状況がよくないっていうことはわかっていました。まわりを見る余裕なんか全然なくて、目の前のことで精一杯。私たち、明日はどうなっちゃうんだろう? この状況はいつまで続くんだろう? って、とにかく不安で。原発事故があったっていうニュースを地震の直後に見た記憶はないんですよ。子どもだったからっていう言い訳はしちゃいけないのかもしれないけれど、もし情報があったとしても理解できなかったでしょうね」
怖かったのは、目に見えない放射能より余震の揺れ
卒業式は先延ばしになった。楽しみにしていた春休みも「さあ、遊ぶぞ!」という気持ちにはなれず、そもそもインドア派であるふゆきさんは、ゲームで気持ちをまぎらわせていたという。
記録によると、ふゆきさんの住む街にも3月15日には放射性物質を含んだプルームが到達し、空間線量を急上昇させている。情報をキャッチして、このタイミングで避難という選択をした住民も少なくない。
当時の曖昧な記憶をたどっていくふゆきさん。記憶に残っている外出といえば、4月から通う中学校の制服類を買うために、両親の車で駅前まで行ったことくらいだ。
「親に放射能汚染のことであれこれ言われた記憶はないんです。食べたらダメだって言われたものもなかったと思います。あのときは、入手できたものを食べるしかなかったし、制限していたら何も食べられない状況だったんですよね。親も気にしていたとは思うのですが、食べざるを得なかったのでしょうね」
中学校に入学したふゆきさんは、好きな絵を気ままに描いて過ごした。原発や避難のことが友だちや先生との間で話題になることは、まったくなかったという。かろうじて覚えているのは、入学当初、校庭の除染が終わるまで外で体育の授業ができなかったことくらいだ。誰かに『マスクをしよう』などと言われた記憶もない。みんなが怯えていたのは、目に見えない放射能ではなく、余震の揺れだった。
「原発事故については、知ったところで私にできることなんて何もないし……という気持ちだったような気がします。今思えば、ですけれど。両親もどっちかというとドライな人間で、『確かに心配だけど、今ここで騒いだって仕方ないでしょ』っていう感じでしたね。子どもに不安を与えちゃいけないっていう気持ちもあったのかな。当時の私は、そんな両親の様子を見て、危機感を持つ必要はないと思ったのかもしれません。本当に、当時は何も考えていなかったんですよ」
髪を染める子、夜のバイトをする子、いつのまにか来なくなる子など、いわゆる“やんちゃ”な子が多かった高校生活は、なかなか楽しかった。「いろんな子がいるものだな」と客観的に眺めつつ、ふゆきさんも中学時代にかけていたメガネをやめ、お化粧をするようになった。小さな頃から大好きだった絵に関する仕事に就きたい、と思うようになったのもこの頃だ。自分の取り柄は絵しかない。そう思っていたのだという。
「私は専門学校に進みたかったんです。絵に関する仕事をしていくには、実践的なことを学ぶのが大事だと思っていて。それには専門学校が一番ですよね。でも、父は大反対。『専門学校っていうのは、本来なら大学で4年かけてやることをぎゅっと短縮してやるところなんだ。大学に行って、学問として学ぶべきだ』って。私は絵に関することを学問として学ぶっていうのはナンセンスだと思っていたから、揉めましたね。もともと、父のなかには、私に政治関係の大学に行ってほしいっていう希望があったんです。さすがにそれは興味もないし、自分の学力で行けるとも思えない。だから、『大学には行くけれど、私がやりたい分野、私がちゃんと4年で卒業できる分野に行かせてくれ』って土下座して許してもらって、自分が望む分野の大学に行くことになりました」
“いつも通り”に終わらなかった甲状腺検査
卒業制作に勤しんでいた大学4年生のときに、5巡目の甲状腺がん検査を受けた。
「異常がなければそれでいい。無料だし、デメリットがあるわけではないし、とりあえず受けておこう」という気持ちで、これまで欠かすことなく受け続けてきた検査だ。
覚えているのは、車を運転していた父親が道に迷って、検査の時間に遅刻したことだ。遅れたらキャンセル扱いになると言われていたのでイライラするふゆきさんと母親を横目に、父親は「わかりにくい場所にある方が悪い」とぼやくばかり。あのときは「怒りの頂点だった」と振り返る。
そんな思いでたどりついた病院で、検査は“いつも通り”に終わるはずだったが、そうはいかなかった。エコー検査の技師は、ずっと同じ箇所を見ながら首をかしげている。終わったかと思ったら、今度は別の技師を呼んできて、2人で同じところを繰り返し見ている。
終わって外に出たら、自分より後に入った家族はずいぶん前に診察室から出てきていた。
「変だな、とは思ったのですが、悪くても、経過観察くらいかなって。気にならなかったと言えば嘘になるけれど、結果が手元にあるわけじゃないから、今気にしたところで仕方ないよな、と思った記憶があります」
検査結果は、「要精密検査」だった。
ふゆきさんが住んでいる地域では、精密検査を受けられる病院が限られている。リストに載っていたいくつかの病院のなかから一番近くにあった病院を選んで、当日ふゆきさんは一人で出かけたという。
一般的に考えて、大学4年生の女の子にとって、がんの精密検査を一人で受けに行くのは心細さを感じるものではないだろうか。
そんな問いは、ふゆきさんにとって逆に不思議なものだったのかもしれない。
「うーん、話を聞くだけだし、こっちから説明することもないし。ちゃんと聞ければそれでいいんだよね? それなら一人で大丈夫でしょ? と思って一人で行くことを決めたんだと思います」
ふゆきさんは、その場で穿刺吸引細胞診をすすめられた。
首に針を刺して細胞を採る検査だ。この検査を経験した人からは、恐怖と激痛について聞くことが多い。大人でも、ひるんでしまう人は少なくないだろう。
「針を刺すって言われときは、おお!と思ったけれど、そんなに怖いとは思わなかったかな。それをしないと結果がわからないのであれば、するしかないよなっていう感じでした」
成人しているので、親の承諾を得なくとも、自分で書類にサインをすれば今すぐ検査を受けられると言われて、ふゆきさんは迷わずサインをした。親に電話をかけたが、それは単に「検査をすることになったから、帰りがちょっと遅くなる」という連絡のためだったという。
針は3回刺すと言われた。時々、うまく細胞が採れていないことがあって、その場合は後日また出直してこないといけないから、「申し訳ないけれど、今ここで3回採らせてほしい」と医師が頭を下げたのだという。
「横になって、けっこう長い時間、ずっと首を伸ばしていないといけないからつらかったけれど、激痛というほどではありませんでした。たしかに、針が入ってくる不快感はあったけれど、でも、すっと入ったっていう感じです。後になって、他の原告さんから、先生に押さえつけられたとか、めちゃくちゃ激痛だったとかいう話を聞いて、びっくりしましたね。まじか! と思いました。私の先生はベテランだったので、上手だったのかもしれません」
「何があっても、感情的になるな」
細胞診の結果も、ふゆきさんは一人で聞きに行った。
がんかどうかの診断を一人で聞きに行くというのは、がんだった場合、その衝撃の第一波を一人で受け止めるということだ。自分の体のこととはいえ、それは決して簡単なことではないだろう。
「うちの家族には、基本的に『ひとりでできることはひとりでする』という暗黙のルールみたいなものがあるんですよね」
ふゆきさんはそう言って笑う。
結果は、検査をしてくれた医師から直接告げられた。
甲状腺乳頭がんだ。すでに1センチを超えているという。
「今すぐ死ぬような病気ではないけれど、ほったらかしにしていいものではない。つらいのは重々承知だけれど、医者としては1センチを超えるがんだと手術をすすめないといけない」。医師はそう説明した。
「手術が怖いとかイヤだというよりも、そういうルールなんですね、と受けとめました。それ以上は、何とも思わなかったかな。ああ、そうですかっていう感じです。他の原告さんが、告知の場でいきなり医師から『原発事故との因果関係はありません』と言われてびっくりしたと言っていたけれど、そういうことは私は言われませんでした。これまでに接したどの先生からも、原発事故という言葉は一度も出てないですね」
ふゆきさんが裁判のために用意した意見陳述書には、告知を受けたときの気持ちについて「無」だった、と書かれている。それはどんな種類の「無」だったのだろうか。
「ちゃんと話を聞いて状況を理解しないと、これから待ち受けているものに対応できないと思ったので、とにかく今はしっかり聞かなくちゃと思って。それ以外の感情はなかったんですよね。そういう意味での「無」です。涙は出ませんでした。たかが手術、という思いもあったかな。手術をしないと後々大変なことになるんだっていう認識があったので、びくびくする暇があるんだったら、今すぐにでも手術を受けて楽になろう、と思ったんです」
告知を受けた病院では手術を受けられないため、新たに病院を決めなければならない。ふゆきさんはその場で細かな判断をせずに、いったん持ち帰って両親に相談することにした。
娘から「がんだった」と告げられた両親も、落ち着き払っていたという。とはいえ、これまで元気だった娘ががんを宣告された衝撃は、決して小さなものではなかっただろう。
「もともと、うちの家族は喜怒哀楽が激しい方ではないんですよ。父には昔から『何かあったときに感情的になったら、一番被害を被るのは自分だぞ』とよく言われていました。そのせいか、私自身のなかに、パニックを起こしても仕方ないよなっていう気持ちが常にあったんです。だから、家族で話したのは、どこの病院で手術を受けるのかとか、そういう実務的なことだけでした」
「がんの当事者」になるまでは、他人事だった
ちなみに、ふゆきさんのがんが見つかったのは、5巡目の検査だ。
でも、つい最近まで、ふゆきさんはそれが4巡目だったと勘違いしていたのだという。というのも、1巡目の検査を受けた記憶がまったくないのだ。
「記憶がない」という言葉から、危機感や不安感を抱くことなく、言われるままに検査を受けに行ったふゆきさんの姿が浮かんでくる。
ふゆきさんの記憶のなかにある友人たちも、原発事故の影響を気にしていた様子はないし、彼女たちとそうしたことを語り合った記憶もない。
「当時は、結局、他人事だったのかもしれませんね。甲状腺がんになった子がたくさんいるっていうことは知っていたけれど、私はがんじゃない。がんじゃない私が何か手助けをしようって言ったって、何ができるの? って。がんになった子たちと触れあったとしても、その人たちの気持ちにはなれないし、わかってあげられないし、結局、何もできないでしょうっていう気持ちだったのかな……」
言いよどみながら、「すみません、ちょっと言いたいことが言えてないような気がする」と、ふゆきさんは次の言葉を探した。
「それは、がんになっていないこちら側の自分と、がんになってしまったあちら側の子どもたちとの間に溝があるように感じていた、ということ?」と問いかけてみる。
「そうですね。それを飛び越えていく必要が私にあるのか? 逆に飛び越えたところで……ということを、どこかで考えていたような気がします。何かすると言っても、話を聞くことぐらいしかできないと思うし、それなら私じゃなくてもできることじゃん? って。結局、自分は関係ないという思いが、どこかにあったのでしょうね」
そう思いながらも、甲状腺がん検査については、「何か異常があれば、いやな思いをするのは自分だから」という理由で欠かさず受けてきた。
まわりの友人のなかに甲状腺にかかった子がいるかどうかは、今でもわからないままだ。
「甲状腺がんに限らず、そもそも病気になったときに友だちに言うか? っていうと、言わないですよね。家族には隠せないと思うけれど、友だちとか職場の人に自分から病気のことをすべて言えるかっていうと、私は無理だと思うんですよ。だから、まわりに甲状腺がんの子がいたのかどうかは、知りようがなかったっていうのもあると思うんです。こっちからわざわざ聞くこともないじゃないですか? だから、いたのかどうかはわからないままですね」
どこか他人事だったという甲状腺がんの問題。自身ががんを告知されたことで、ふゆきさんは一瞬にして「あちら側」に立つことになった。
「そのときは、立場が変わったとか、そういうことを考えている余裕はなかったですね。目の前の状況を受け入れないといけないけれど、わからないことだらけだし、受けとめ切れない部分も多かったし。それ以上、何かを考える余裕はなかったような気がします」
[ライタープロフィール]
棚澤明子
フリーライター。原発や環境、教育、食など、社会課題を主なテーマに執筆。著書は『福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を』『福島のお母さん、いま、希望は見えますか?』『いま、教育どうする?』(弘田陽介氏との共著)(すべて彩流社)ほか。16歳、19歳の男の子の母親。