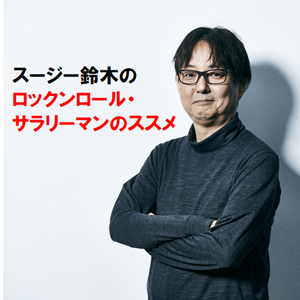第9回 標準語禁止のオフィスを作ろう
スージー鈴木
「ごくごく簡単に、高校球界最強の野球部を作る方法」というのを思いついたことがあります。それは――「丸刈り禁止」。
全国には、野球がめっちゃうまいのに、丸刈りが嫌で、サッカーとかバスケを選択したフィジカルエリートが、けっこういると思うのです。そんな彼らを全国から誘引する「丸刈り禁止」の野球部を設立すれば、けっこう簡単に甲子園に行ける……かも。
ま、実際は、そんなに簡単ではないと思いつつ、ポイントは「長髪OK」ではなく「丸刈り禁止」とするところにあります。だって日本の高校球界の場合、「長髪OK」と言われても、何となくの同調圧力で丸刈りにしてしまう球児が多そうだから。
さて、「ロックンロール・サラリーマン」の「ロックンロール」は、ここまで書いてきた通り、会社員という立場に縛られず、別の世界でも自己表現することを表しています。でも、より本質的には、会社仕事も含めて、自分らしい自由な考えを発信しながら仕事をしようという意味を込めているのです。
会社仕事が、つまらない同調圧力から解放されて、みんなの自分らしい自由な意見やアイデアで溢れていたらいいなぁ。いいでしょう?
そうなるためのアイデアをご紹介します。これ、多くの読者は冗談と受け取るかもですが、私は本気で提案します。アイデア料は要りませんので、この素晴らしい考え方を、どんどん導入してください。
──「オフィスを標準語禁止にする」
こんなことを思い付いたのには、私自身の経験が関係しているのです。

大阪弁のパワーをフル活用した嘉門達夫、初期のアルバム
●大阪弁で会社仕事が突然いきいきとし始めた
1990年、バブル真っ盛りの広告会社に入社したのですが、そんな時代のそんな業界、オフィスの共通語は、完全に標準語でした。もちろん新人の私も、標準語を使っていました(今から考えれば、私の標準語、割とうまかったと思うのですが)。
しかし、仕事がうまく行かず、数年間、悶々とした日々を過ごしていたある日、思いついたのです。「大阪弁でしゃべってみても、ええんちゃうか?」と。
ご存じのように、数ある方言の中で大阪弁/関西弁は比較的、市民権を得ていますので、そういう意味ではラッキーで、かつ当時は、ダウンタウンが大ブレイクしていた頃だったので、思い切って、大阪弁を、自分の標準言語にしてみたのです。
すると、どうでしょう。仕事がうまく回り始めたのです。おそらく大阪弁が、私の個性を引き出したのでしょう。
なぜ、うまく回りだしたのか。第一義的には、単に私の大阪弁が面白がられて、可愛がられたということでしょうが、より本質的には、「母国語」の大阪弁で考えるからこそ、私のアイデアや意見に、私ならではの独自性が備わったのではないかと思われます。
言語は思考を規定します。借り物の標準語で考えると、頭で考えた借り物のアイデアしか出てこない。でも身体にぴったり馴染んだ方言で考えると、頭ではなく、身体の奥底から湧き出てきた、まさに自分ならではのアイデアを吠えたくなる!
という、私自身、n=1の経験に汎用性があるならば(あると信じています)、オフィスを標準語禁止にして、各地の方言が乱れ飛ぶ、日本全国の文化と風俗を凝縮したオフィスにすれば、上で書いたような意味でのロックンロールな業務環境が出来上がるのではないか。
冷静に考えれば、やはり大阪弁は特別かと思うのですが、でも、あまりにもローカル過ぎる表現だけ控えれば、方言オフィス、成立すると思います。それに、何といってもこの施策、経費ゼロ! タダでできる施策なのですから。
まずは、特にアイデア会議とか、ことさら自由な空気が求められるシーンから始めてみるのがいいでしょう。繰り返しますが、私にアイデア料は要りません。逆に、成果が出たらレポートを送ってください。
──と、この原稿、一気に書いたら身体がえらいわぁ……。この「えらい」のニュアンスを体現する言葉が標準語に存在しないと、かねてから私は思っていました。「えらい」が伝われへんオフィスって、身体や心が「えらい」と思(おも)てる社員に、目配りせえへん心無いオフィスなんとちゃうやろか?
[ライタープロフィール]
スージー鈴木(すーじーすずき)
音楽評論家、小説家、ラジオDJ。1966年11月26日、大阪府東大阪市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。音楽評論家として、昭和歌謡から最新ヒット曲までを「プロ・リスナー」的に評論。著書・ウェブ等連載・テレビ・ラジオレギュラー出演多数。
著書…『桑田佳祐論』(新潮新書)、『EPICソニーとその時代』(集英社新書)、『平成Jポップと令和歌謡』『80年代音楽解体新書』『1979年の歌謡曲』(いずれも彩流社)、『恋するラジオ』『チェッカーズの音楽とその時代』(いずれもブックマン社)、『ザ・カセットテープ・ミュージックの本』(マキタスポーツとの共著、リットーミュージック)、『イントロの法則80’s』(文藝春秋)、『サザンオールスターズ 1978-1985』(新潮新書)、『カセットテープ少年時代』(KADOKAWA)、『1984年の歌謡曲』(イースト新書)など多数。