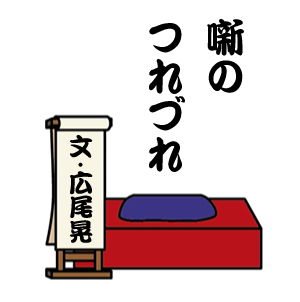その2 落語は「都会人」のもの
広尾晃
「落語とは何か」前回から続く。
本当にそうだったのかはよく知らないが、昔の東京や大阪では、田舎から子どもが商店に奉公にやってくると、主人に連れられて寄席のお供をしたという。落語の世界にふれて、都会の商家のマナーや、人付き合いの機微を学ばせるためだったという。
落語には下層階級ともいうべき人が出てくる。「らくだ」の馬さんや紙屑屋、「長屋の花見」の長屋の住人、「あわびのし」の気楽な亭主。蓄えなど全くない、その日暮らしの登場人物たちだ。
こうした人々が出てくるから、落語は一般庶民の、気安い娯楽だったと思われがちだが、そうではない。
寄席という形態がほぼ固まるのは、東西ともに江戸後期だ。この時期は、都市での商業が盛んになり、商人階級が富を得るようになった時代だ。
この時期、都市には職を求めて地方から人々が流入するようになった。江戸時代の人たちは、今でいう戸籍に近い宗門人別改め帳に記入されることで、国家、幕府から身分を保障されていた。どこかの寺の檀家になることが、身分保障だったのだ(寺檀関係)。しかし、地方から流入する人は、寺壇関係を断ち切って勝手にやってきた人が多かった。こういう人々が、商人階級、その下の職人階級のさらに下に階層を作って生活していたのだ。これを「無宿人」という。下層階級の人々の多くは無宿人上がりだった。
この辺、ちょっと今の中華人民共和国に似ている。
我々の感覚では、長屋というと貧乏人が住んでいそうな気がするが、長屋にもランクがあった。
表長屋と言われるものは、店舗付きのものもあり、今でいうマンションに近かった。落語でいえば剣道(「やっとう」と言う)の師匠や二号さん、手習いの師匠が登場する「三軒長屋」の長屋は、表長屋だっただろう。大きな商家の通いの番頭なども表長屋に住んだ。表長屋には小さな庭があるものもあった。
武士も大名、旗本屋敷の敷地にある長屋に住んだ。この場合「御長屋」と敬称をつけた。
これに対し、無宿物や貧窮者、曰くのある人間などは「裏長屋」に住んだ。家賃も安いが一軒の家を薄い壁で仕切った棟割長屋であり、衛生状態も悪かった。
こうした裏長屋は、落語の登場人物にはなったが、住人達は文字通り食うや食わずの人が多かったから、寄席などに行く余裕はなかった。
寄席で遊ぶことができたのは、「表長屋」に住むような、生活に余裕のある人々だった。寄席で人々は、落語や色物(漫才、曲芸、音曲など)などを楽しんだ。同時に、人々は落語を通して「都会人の生き方」を学んだとされる。
落語には、様々な噺がある。その世界も、価値観も実に多様だ。努力をすることで報われる噺もある、主君や主人の温情を感じる噺、夫婦の愛情をテーマにした噺、気楽な長屋暮らしを描いた噺。
しかしながら、そうした噺の基調となっているのは、「人との距離感」ではないかと思う。
田舎の人々は、家族、血族者、何代もの顔見知りが一緒に暮らしている。人々の関係はなれなれしく、緊張感がない。当然、コミュニケーションもこなれたものになる。公私の別はそれほど厳しくなく、プライバシーも緩い。
これに対して、壁一枚隔てて赤の他人が住んでいる都会では、常に緊張感のあるコミュニケーションが行われている。それだけに礼儀作法やマナーにも一定のルールが求められる。人付き合いにしても、外面は愛想が良いが、プライベートには立ち入らせない冷たさもある。
「いわいのし」「牛ほめ」などの落語を聞いていると、大家や親せきなどに祝いの言葉を述べるにしても一定のルールがあったことが分かる。
人いきれがするほど多くの人がひしめいて住んでいた都会では、人との適度な距離感を取るための暗黙のルールがあった。これを田舎出の子どもに学ばせるうえで、寄席はなにがしかの貢献をしただろう。
同時に、寄席は「努力すれば必ず報われる」という上昇志向では説明できない、人生の「もう一つの面」をさりげなく見せもした。
世の中は成功者ばかりではない。努力しても報われなかった者、敗残者。そもそも努力をしなかった人間も生きている。こういう人たちの生活や価値観をさりげなく見せる役割も果たしただろう。
落語には、どうしようもない人間がたくさん出てくるし、悪いことをして成功する人間も出てくる。そうしたものまで、そのまま投げ出すのが落語だ、ということもできよう。
故五代目立川談志が「落語とは(人間の)業の肯定だ」といったのは、まさにこのことだ。
この部分ばかり強調するのはやや危険な気もするが、落語には、確かに人間の「裏」の部分を垣間見させるような部分もあったのだ。
そういう意味で、落語という芸能は、「都会」でしか成立しないともいえる。
昔の田舎では、落語にしばしば出てくるような犯罪者やアウトローは生きていくことができない。
極言すれば、落語は東京と関西(大阪、神戸、京都)でしか成立しえないものだと言っても良いだろう。
明治期に入り、東京に薩長をはじめとする地方から人々が押し寄せた。寄席にもこうした“田舎者”がやってきた。彼らのニーズに応えるべく、寄席には「珍芸四天王」と呼ばれるばかばかしい演芸をやる一派が現れた。これまでの東京人はこれをさげすんだが、彼らによって、寄席は大いに盛り上がった。
しかし、時間の経過とともに地方人も都会化し、江戸前の渋い落語を好むようになった。
一方で、同じように地方から人々が流入した関西では、漫才など「色物芸」が隆盛を極め、落語は下火になった。ほとんど滅びていたものが、戦後、六代目松鶴、三代目米朝、三代目春団治、五代目文枝の「上方四天王」らの奮闘によって、再び隆盛を見るようになった。
今、落語が栄えて、全国的に人気があるのは、落語に見る「都会型の価値観」が、地方にも共有されるようになったことが大きいと思われる。
つまり「地方の都市化」が、落語人気を後押ししているのだと思う。
ただ、今も、落語の愛好者は、どちらかと言えば高学歴者、趣味人などが多い。テレビのバラエティや漫才などとは少し客層が違うのは事実だろう。
[ライタープロフィール]
広尾晃(ひろお こう)
1959年大阪市生まれ。立命館大学卒業。コピーライターやプランナー、ライターとして活動。日米の野球記録を取り上げるブログ「野球の記録で話したい」執筆。また文春オンライン、東洋経済オンライでも執筆中。主な著書に『プロ野球なんでもランキング 「記録」と「数字」で野球を読み解く』(イースト・プレス、2013年)『プロ野球解説者を解説する』(イースト・プレス、2014年)『もし、あの野球選手がこうなっていたら~データで読み解くプロ野球「たられば」の世界』(オークラ出版、2014年)『巨人軍の巨人 馬場正平』(イースト・プレス、2015年)『ふつうのお寺の歩き方』(メディアイランド、2015年)『野球崩壊 深刻化する「野球離れ」を食い止めろ』(イースト・プレス、2016年)『奈良 徹底的に寺歩き 84ヶ寺をめぐるルート・ガイド』(啓文社書房、2017年)等がある。