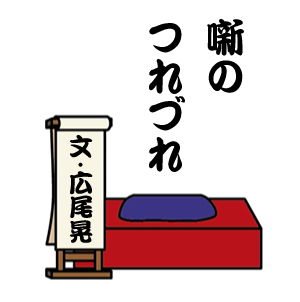その5 「新作落語」と「古典落語」
広尾 晃
「古典落語も生まれたときは新作だった」という言葉があるが、そうではない。古典落語の多くは、生まれた時から古典だった。
落語が生まれる以前の「聊斎志異」にまとめられたような中国説話、「今昔物語」など日本の説話や地域伝承などから古典落語は生まれた。生まれた時から十分にこなれていたのだ。
「古典落語も生まれたときは新作」という言葉は新作落語を作る側から発せられる言葉だ。だから、「面白くなくてもご勘弁」なのか、「古典と同じように大事」なのかわからないが、浅いものの見方だと思う。
古典は、落語のネタになった時点で、完成度の高い物語だった。これに何世代もの名人上手が演出を加え、解釈を考え、練りに練って今の古典落語になった。素材が良かったから、多くの噺家が高座に掛けたがったし、手を加えたがった。こうして逸品ともいえる落語が出来上がったのだ。
新作には、こうした時間的な熟成も質的な深まりもない。もともと、古典落語と拮抗するようなコンテンツではないのだ。その認識があるかないかで、新作落語への評価は大きく変わると思う。
新作落語の定義は難しいが、戦後に作られた落語、およびそれを演じる噺家の一派という風に考えると、いくつかの流れが存在する。
一つは、五代目古今亭今輔、その弟子の四代目桂米丸、三代目三遊亭圓右、同じ芸術協会の三笑亭笑三らのグループの新作落語。いわゆる「山田くーん」ものである。五代目今輔は、戦後すぐに入門してきた米丸の資質を見込み、古典を一切教えず、新作一本の噺家にした。この米丸を中心に落語芸術協会の噺家が、戦後の新しい“庶民”だったサラリーマンの生態を描いた新作を多数作ったのだ。
朝日新聞に掲載されたサトウサンペイの4コマ漫画の世界と言えばよいかもしれない。昭和20年代、30年代は新鮮に映ったことだろう。しかし、私が落語を見始めた昭和40年代にはすでに古い臭いがしていた。
「山田君、がんばりたまえよ!」という上司はもう会社にはいなかったし、「タクは、今夜は張り込んでビフテキざあますの」という奥様もご近所にはいなかった。ステレオタイプのキャラクター設定が、時代についていけなかったのだ。新作はみるみるうちに陳腐化したのだ。
また、笑いの質も上等とは言えなかった。三笑亭笑三は、マイカーの小噺を良く振っていた。今日は朝からドライブだと言うので、ご主人が家族にいろいろと準備をさせる。忘れ物はないか、さあ出発だというところで、「ガソリンが入っていなかった」というもの。何度か聞いたが、客席でただの一人も笑ったのを聴いたことがない。底の浅さは明らかだった(ただ、私は、今、百歳に迫ろうとする米丸の落語を聴いて、いいなと思うことが多くなった。四半世紀が過ぎ、昭和を歴史的な「時代」として客観視できるようになったからだろう。これはこれで貴重だと思う)。
この芸術協会の新作落語のアンチテーゼとして、昭和50年代に東西で呼応するかのように、新しい新作落語の流れができてくるのだ。
東京では先ごろ物故した三代目三遊亭圓丈が主宰する「実験落語の会」。関西では桂三枝(現六代目文枝)が主宰する「創作落語の会」。
東京は「“山田くーん”はいやだ」という思いで始めた会だった。圓丈、夢月亭歌麿、柳家小ゑん、立川談之助など若手中心の顔ぶれ。キッド・アイラックホールなど、中小演劇の劇場などで開かれた。
関西は、漫才ブームに刺激されての運動だった。三枝、文珍、八方など吉本系の噺家が多かったがメンバーは固定されていなかった。大阪キタのバーボンハウスで行われていた。
いずれも、時事ネタや流行など今の話題性を取り入れていた。語り口も自由、ジーパン姿で立って噺をするものもいた。また、着物もローリングストーンズのロゴを入れたり、ラメが入ったり、奇抜な演出をしていた。
大学生だった私は「実験落語の会」に共鳴して、夜行列車で東京に行き、噺家の家に泊まり込むなどしていた。ついには、大阪で小ゑん、談之助の落語会を開催したりもした。
関西の「創作落語の会」は、吉本の劇場でかけられる漫談風のものも多く、新鮮味に欠けたために、私は「実験落語」を贔屓していたのだ。
しかし、「実験落語の会」は、圓丈を除いて力量的には見劣りした。あるとき、上野鈴本での「実験落語」の公演にシティボーイズが客演したことがあった。大竹まことの狂気の舞台と比較した時に、「実験」の顔ぶれはあまりにも貧相だった。
三遊亭圓丈は、晩年まで独自の「実験落語」を公演し続けていた。しかし「実験落語」は大きな流れとはなりえなかった。
同様に、桂三枝も「創作落語」を創りつづけ、芸術祭賞も獲得した。今では220本もの創作落語のレパートリーがあるという。これは確かに偉業だ。しかし、落語の新しい流れを作ったというには躊躇がある。三枝は現代を素材として古典落語の手法で料理しただけではないのか、と思うのだ。確かに達者で、聞きごたえはあるが、表現としての新しさはなかった。深まっていないとも思った。
これが「新作落語」の進化した形だとはとても思えなかった。
なお、こうした大きな流れとは別に、古典落語の世界で「新しい噺」を創作する動きは、常にあった。
四代目桂米団治「代書」、三代目桂米朝「一文笛」、三田純市「まめだ」、織田正吉「怨み酒」、小佐田定雄「幽霊の辻」「貧乏神」、筒井康隆「妊娠」、林家染語楼「青空散髪」、桂文紅「ぜんざい公社」など、上方での動きが多いが、東京でも今村信雄「試し酒」、岡鬼太郎「強情」などがある。
完成度の高い作品が多いが、これらは「擬古典」というべきものだ。
今世紀に入って、これまでの新作落語とは軌を一にする噺が、主に東京の落語家によって創作されている。立川志の輔「バールのようなもの」「みどりの窓口」「歓喜の歌」、柳家喬太郎の「ハワイの雪」。
これらの噺を聴いていると、「舌で描く芝居」という落語の定義が、音を立てて変わりつつあることを実感する。彼らが舌で描いているのは、芝居=歌舞伎ではなく、現代劇や映画なのだ。そしてそれを描くための話芸、技術を自分で磨きこんでいる。
志の輔や喬太郎などの噺家は、「自身が表現したいもの」のために、新しい話芸を創出しつつあるように思う。
これこそが「新作落語」の進化系ではないか、と今、私はときめいている。
[ライタープロフィール]
広尾 晃(ひろお こう)
1959年大阪市生まれ。立命館大学卒業。コピーライターやプランナー、ライターとして活動。日米の野球記録を取り上げるブログ「野球の記録で話したい」執筆。また文春オンライン、東洋経済オンライでも執筆中。主な著書に『プロ野球なんでもランキング 「記録」と「数字」で野球を読み解く』(イースト・プレス、2013年)『プロ野球解説者を解説する』(イースト・プレス、2014年)『もし、あの野球選手がこうなっていたら~データで読み解くプロ野球「たられば」の世界』(オークラ出版、2014年)『巨人軍の巨人 馬場正平』(イースト・プレス、2015年)『ふつうのお寺の歩き方』(メディアイランド、2015年)『野球崩壊 深刻化する「野球離れ」を食い止めろ』(イースト・プレス、2016年)『奈良 徹底的に寺歩き 84ヶ寺をめぐるルート・ガイド』(啓文社書房、2017年)等がある。