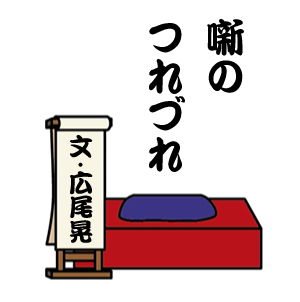第7回 心やすい“昔の上方”が、たちあがってくる 五代目桂文枝
広尾 晃
現六代目桂文枝は、もとは桂三枝。吉本興業の大スターとして圧倒的な存在だったが、師匠の名前を継いで2012年に六代目桂文枝になった。個人的にお世話になったこともあり、五代目文枝(1930-2005)が過去の人になることは、さびしい気がしたものだ。
六代目文枝は、五代目の総領弟子であり、名跡を継ぐことに何の問題もないが、芸風は全く似ていなかった。
五代目文枝の代表作といえる演目を2つ紹介する。
■「愛宕山」
五代目文枝は、長い間三代目桂小文枝を名乗っていた。上方落語協会の会長に就任した時も小文枝だった。上方落語四天王のひとりとして、すでに一流をなしていたが、文枝を襲名し、六十歳を超えたころから、一層華やぎを増したように思う。
もともとやや臭め(くどい)の演技だったが、このころから大げさな演技がすんなりと聞きやすくなった。「芸が大きくなった」とはこういうことかもしれない。
春先、芸妓、舞妓、幇間を引き連れた豪勢な野遊びの風景。文枝が演じると、舞台がぱっと華やぐ。上方の世話物の芝居の幕が開いたようなあでやかさ、ときめきがある。
この噺を得意とする噺家は、東西に多いが、愛宕山に登るまでの賑やかさ、楽しさは文枝に尽きるだろう。
頭のてっぺんから出るような嬌声も、大げさな所作も、まったく嫌みがない。たった一人で舞台をここまで明るくすることが出来るか、と思えた。
春霞が漂うような導入部から、かわらけ投げへと舞台が変わる中盤、演者は、物見遊山の華やぎの中から、若旦那と幇間一八の確執のドラマをせり出させなければならない。
文枝は、ここで屈託のある幇間一八をリアルに描く。若旦那への反発、金への執念、そんなぎらぎらした情念が、春霞を霧消させ、噺はにわかに緊迫感を帯びる。
クライマックスは、傘を手に谷底へ飛び降りた一八が、竹をしならせてその反発で揚がろうとあがくシーンだ。
「いま行きますさかいになあ、待っとくなはれや」
熱に浮かされた病人のように、文枝演じる一八はこの言葉を繰り返すのだ。そこには黒光りするような“慾”と“執念”が、ごそっと音がしそうな手触りで存在している。華やかな芝居を現出して見せた文枝は、ここにきて、非情なリアリストになるのだ。聴衆はぐいぐいと引き寄せられる。
そしてさげへ。切れ味のいい大団円が待っている。快感がある。
何度も文枝のこの噺を聞いたが、いつでも精気に満ち溢れ、素晴らしい出来だった。
七十歳を超えても血色がよく、一流企業の重役のような貫禄があり、いつも上機嫌だった文枝。その突然の訃報に驚いたものだ。
■「船弁慶」
この落語は、エンディングは芝居がかりになる。率直に言って、今の人になじみ深いわけではない。むしろ、導入部に魅力がいっぱい詰まっている。
夏まっさかりの大阪である。むっとするような暑気の中、清八が主人公の喜六を遊びに誘いに来るところから話は始まる。舟遊びに連れ出す話がまとまりかけた頃、喜六の女房おまつ(しゃべくりがすごいので、雀のお松と呼ばれている)が外出から帰ってくる。昨夜は親類の家に泊まってきたことを夫に聞かせるため、近所のおかみさんにべらべらと話し出す。
このくだりが最高だ。叔父が病気だと聞いて訪れた女房は、実際は大したことはなかったのだが歓待を受け、泊まってしまう。翌日、帰ろうとすると素麺を出され、ついつい長居をした上に昼寝までしたために帰りが遅くなってしまった。
言葉にするとこれだけだが、女房の口を借りて立て板に水の勢いで話すうちに、昔の庶民の家の生活の匂いがたちあがってくる。そうだった、昔は、心やすい親戚が近くにいて、よく遊びに行ったものだった。夏場など必ず「素麺食べていき」と言われたものだ。
まだ世の中がそれほど世知辛くなく、みんなが緩くつながり合いながら生きていた時代の、懐かしい光景が、先代文枝の口を借りて再現されるのだ。もっちゃりした口調は、まさに古き良き大阪の味そのものだった。
この落語は今も多くの上方の噺家が高座に掛ける。おまつのくだりは、どの噺家も達者で、面白いが、先代文枝ほど濃厚な味わいを出せる人はいない。
目から鼻へ抜けるような才気は感じさせなかったが、先代文枝には、大阪の水で育った噺家ならではのこなれた味わいがあった。
大家の旦那のような悠揚迫らぬたたずまい。いつもにこにこと機嫌よくて、我々のような若いものにも親切だった。
私が上方落語協会を退職するときには、自身がCMをやっていた「千日堂」という料理屋で送別会を開いてくれた。
この師匠は当時の噺家としては珍しく、大阪市交通局で働いていたことがあり、サラリーマンの経験があったのだ。だから送別会を開いてくれたのかもしれない。
「上方落語四天王」では、六代目松鶴に次いで世を去った。どういう縁なのかはわからないが、三重県伊賀市の病院で息を引き取ったのだと記憶している。
阿倍野区の葬儀場での告別式に行ったが、多くの吉本芸人が参列していた。
六代目文枝は達者な噺家だが、五代目とは芸風が違う。「船弁慶」はやらない。ただ文珍やきん枝、さらに文太など文枝の遺産を受け継いだ弟子がいる。
先代文枝の面影は、こうして伝えられていくのだろう。
[ライタープロフィール]
広尾 晃(ひろお こう)
1959年大阪市生まれ。立命館大学卒業。コピーライターやプランナー、ライターとして活動。日米の野球記録を取り上げるブログ「野球の記録で話したい」執筆。また文春オンライン、東洋経済オンライでも執筆中。主な著書に『プロ野球なんでもランキング 「記録」と「数字」で野球を読み解く』(イースト・プレス、2013年)『プロ野球解説者を解説する』(イースト・プレス、2014年)『もし、あの野球選手がこうなっていたら~データで読み解くプロ野球「たられば」の世界』(オークラ出版、2014年)『巨人軍の巨人 馬場正平』(イースト・プレス、2015年)『ふつうのお寺の歩き方』(メディアイランド、2015年)『野球崩壊 深刻化する「野球離れ」を食い止めろ』(イースト・プレス、2016年)『奈良 徹底的に寺歩き 84ヶ寺をめぐるルート・ガイド』(啓文社書房、2017年)等がある。