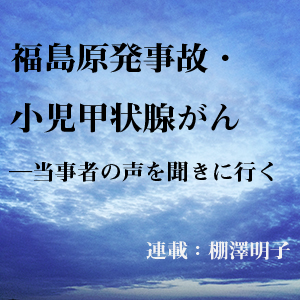第3回 「原発事故との因果関係はありませんから」。あまりに唐突で、マニュアルがあるんじゃないかと思うくらい不自然でした――鈴木ちひろさんのケース(前半)
棚澤 明子
「あの手紙」の女性と感動の再会
鈴木ちひろさん(仮名・27歳)のもとを訪ねたのは、2022年10月下旬のことだ。
バッシングを受けるリスクを懸念し、身元を隠して訴訟を起こしている以上、取材に対する警戒心はきっとあるだろう。そう思い、少しでも安心材料になれば……と、原発事故被害にあった母親たちの“その後”を追った拙著『福島のお母さん、いま、希望は見えますか?』(2019年/彩流社)を持参した。
この本の執筆当時も、私は甲状腺がんに罹ってしまった若者たちの声を聞くべきだと思っていて、いくつかのルートから取材を打診した。しかし、ガードは固く、取材の許可は誰からも下りなかった。
ただ、このとき、当事者やその家族の支援をしている牛山元美医師のおかげで、一通の直筆の手紙を掲載することができた。
手紙は甲状腺がんの当事者である若い女性からで、「甲状腺がん検査を縮小しないでほしい」という強い思いが綴られている。もちろん、名前は書かれていない。
私はずっと、この女性はその後どうしているのだろうか、転移や再発することなく元気に暮らしているのだろうか、と案じ続けてきた。
なんとかして、会えないだろうかと思ったこともあった。
2022年1月、甲状腺がんを患う若者たちが東電を提訴したというニュースが流れた。
手紙の女性のことが再び気にかかるようになる。彼女は原告に加わっただろうか。それとも、もうがんのことなど忘れて元気に暮らしているのだろうか。
取材の当日。
部屋に入ると、私の少し後にやわらかな笑顔の若い女性が入ってきた。取材に応じてくれたちひろさんだ。
挨拶を済ませて本を手渡す。「実は、前回の本でも甲状腺がんの問題については触れているんです。こうしてお手紙を寄せてくださった方もいて……」と、手紙が掲載されたページを見せたとき、ちひろさんが目を見開いた。
「あ、この手紙、私です……」
ちひろさんは、あの手紙の女性だったのだ。
原告のひとりとして、立ち上がっていたこと。
今日、こうして元気な姿で目の前に現れてくれたこと。
不思議なご縁への感謝、法廷で闘うと決意したことへの敬意、ひとりの大人として無力であることの申し訳なさ……。
たくさんの気持ちが溢れ、でも、どう言葉にすればいいのか分からなくて、結局、涙になってしまった。
******
放射能の話をしたら、人間関係が壊れてしまう
ちひろさんが生まれ育ったのは、福島県の中通り。小さな頃はやんちゃで、外で遊ぶことが大好きな女の子だったという。
「中学時代では、憧れだった運動部に入部しました。1学年で20人以上もの部員がいたので、メンバーに選ばれるために必死に練習に打ち込みました。部活一色の毎日でした。でも、最後には努力が実って、メンバーに選ばれることができたんです」
充実していて、とても楽しかったという中学校3年間を、ちひろさんはそう振り返る。
2011年3月11は中学校の卒業式。無事に式が終わって家に帰り、夕方から友だちと遊びに行くために着替えて、くつろいでいたときに大きな揺れに襲われた。あらゆるものが落ちてきて床に散乱したものの、幸い家そのものは無事だったという。
しかし、ひとりの親戚の家が全壊してしまった。この方は、足が不自由で歩けない。震災当日は家族で親戚のもとに駆けつけ、今後のことを相談しているうちに夜が更けていった。
翌日、親戚はたまたま向かいにあった空き家に入れることになった。朝から夕方までかけて、家族全員で荷物を台車に載せて運び込む。
18時頃、雨が降ってきた。親戚の当面の住まいとなった空き家にちひろさんが慌てて入ると、テレビを見ていた親戚がこっちを見て言った。
「原発が爆発したみたいだよ」
15時36分、福島第1原発の1号機が爆発したのだ。
「原発のことなんてそれまでまったく知らなかったし、近くにあるなんて考えたこともありませんでした。学校でも一切習っていないと思うんですよ。だから、いきなり爆発したって言われても、驚いたというより『へえ、そうなんだ?』っていう感じでしたね」
チェルノブイリ原発事故を通して放射能の知識があった両親からは、「悪影響があるかもしれないから、ちひろだけは外に出ないで」と釘を刺されたという。
中通りは原発から50キロメートル以上の距離があるため、放射能汚染の被害が少なかったように思われがちだが、空間線量は通常の数10倍、地域によっては数100倍にまで跳ね上がっていた。避難や移住を決断した住民も少なくない。
3月15日に予定されていた高校の合格発表は、学校側の配慮だったのか、電話で聞くことができた。ただ、入学手続きや課題の提出などがあったので、家から自転車で15分ほどの高校には何度か足を運ばざるを得なかったという。
本来なら、進学先も決まって心おきなく遊べたはずの春休みだったが、ちひろさんは両親の言いつけを守って、なるべく室内で過ごすようにしていた。一方で、放射能に関する知識をもたない家庭の子どもたちは出歩いている。
放射能、こわいよね? やばいよね? マスクする方がいいんじゃない?
そんな話はすべてタブーだ。
「放射能を気にするかどうかは人によって違うから、すごくデリケートですよね。あんまり踏み込んで人間関係が崩れたり、居場所がなくなったりするのは怖い。だから、放射能に関することは、まわりの子たちも口に出しませんでした」
社会を揺るがせてはいるけれど、目には見えず、正体がよく分からないもの。それを怖がるのか、気に留めないのかという違いだけで、親しかった仲間たちが簡単に分断されていく。
新型コロナウイルスが流行しはじめた頃も、多くの人が隣の人の顔色を見て、自分の気持ちを飲み込んだものだ。コロナ禍による初の緊急事態宣言が発令されたとき、福島で原発事故を体験した知人が「あの頃の福島の空気と同じだ」とつぶやいたことが印象に残っている。
突然の体重激増と生理不順
ちひろさんが1巡目の甲状腺がん検査を受けたのは高校2年生のとき。学校での集団検診だった。放射能汚染のなかで暮らしていたので不安は絶えず、「検査をして安心できたらそれでいい」という思いはあったが、それ以上のことは深く考えていなかったという。結果は「A2(20mm以下ののう胞または5mm以下の結節あり)」だった。
高校を卒業したちひろさんは、親元を離れて東京の某大学に進学した。昔から憧れていた東京に出るために、がんばって推薦を取ったのだという。
東京での暮らしは、勉強やアルバイトなどで忙しかった。
「検査は、時間ができたときに行けばいいや」
2巡目の検査の通知は届いていたが、そんな気持ちで見送っていたという。
ところが、大学1年生が終わる2月頃、突然体重が8キロも増え、これまで規則的だった生理が2週間に一度くるようになった。おかしいなと感じていると、次には喉に違和感を覚えた。
「それ、甲状腺の症状だよ……」
不安になって母親に連絡を入れると、ずばりと指摘された。甲状腺がんを心配していた母親からは、これまでに何度も2巡目の検査を急かす電話がかかってきていたのだ。
とにかく、早く検査を受けなければ。ちひろさんは、そのときたまたま実施されていた集団検診を受診するために慌てて帰郷した。
2巡目の検査から2ヶ月後の5月、母から電話がかかってきた。実家に届いた検査結果の通知に「B判定(20.1mm以上の嚢胞、または5.1mm 以上の結節あり)」と書かれていたのだという。
「まあ、大丈夫なんじゃない?」
A2からBへと移行したことの意味がよく分からずに軽く受け止めたが、福島県立医大から「早急に精密検査を受けるように」という電話が2度も実家にかかってきたと聞いて、不安がよぎった。
「もしかしたら、私、危ないのかもしれない……」
それからは、尿検査や血液検査、CT検査、穿刺細胞診など、たくさんの検査を受けるために、東京と福島を何度も往復したという。
つらかったのは長い注射針を首に刺して、甲状腺の細胞を採取する穿刺細胞診だ。
「横になった私の上にお医者さんが乗って、ぐっと全体重をかけてくるんです。針がメリメリメリって入ってくる音がする、みたいな感じです。泣きたいわけじゃないのに、痛くて勝手に涙が出てくる。あれは、つらかったですね……」
結果が出るまでの間、ちひろさんは大きな不安に押しつぶされそうになりながらも、真正面から現実を見据えていた。
そもそも、甲状腺がんとはどのようながんなのか。もし被ばくの影響で生じたがんなのだとしたら、どのように進行していくのか。もし本当にがんなのだとしたら、どこの病院で手術すべきなのか。大学は休学しなければならないのか……。
ひたすらインターネットで検索する日々。見ないふりをするのではなく、あえて目を見開いたのは、「不安を解消するために、現実的に何ができるのかを知りたかったからなのかもしれない」とちひろさんは振り返る。
「原発事故との因果関係はありません」
B判定が出てから5ヶ月後の10月末、ちひろさんは母親と一緒に福島県立医科大に呼ばれた。
予定の時間になっても、担当医は手術が長引いているということで現れなかった。バタバタと走りまわる看護師から、申し訳なさそうな顔で「手術がいつ終わるか分からないから、病院内のスタバで待っていてもらえませんか?」と言われる。ちひろさんは母と2人でコーヒーを飲みながら2時間ほど待った。すでに夕暮れ時で、人影はまばらだ。
「なんだかそのときに、この病院は手術がうまくいっていないんじゃないか、というような気がして……。技術的に大丈夫なんだろうか、という不信感のようなものが出てきたんですよね」
ちひろさんはそう振り返っている。
結局、予定していた医師は現れず、代わりの医師と診察室で向き合った。
「甲状腺乳頭がんですね」
医師はパソコンのモニターにちひろさんの甲状腺の細胞を写し出し、紫色に染まっている部分ががん細胞だと説明した。
「忘れられないのは、聞いてもいないのに『原発事故との因果関係はありませんから』って言われたこと。あまりに唐突で、マニュアルがあるんじゃないかと思うくらい不自然でした」
ちひろさんは、その場で「東京のA病院に紹介状を書いてほしい」と頼んだ。診察の直前に感じた不安感や不信感を無視できなかったからだ。
がんだと言われた瞬間に泣きそうな顔をしたという母親は、放心状態で喋ることもできず、帰りは車の運転もできなくなってしまったという。
一方で、ちひろさんは診断される前に「自分はがんなんだろう」という方向に気持ちをもっていっていたので、ショックは受けつつも「ああ、やっぱりそうだったんだな」と受け止めた。頭のなかを巡っていたのは、「この先の治療はどこで受ければいいのだろう、大学はどうすればいいのだろう」という、次の行動についてだった。
決して強いわけでも、ドライなわけでもなく、壊れそうな心を自分の手で必死に守ろうとしていたのではないかと思う。
ちひろさんは、甲状腺がんになったことをほとんど誰にも言わなかった。数人の友人、そして必要に迫られて伝えたゼミの教授とアルバイト先の店長以外、ほぼ口外していない。
「事故直後、避難した人たちが避難先で『福島ナンバーは来るな!』って罵声を浴びせられたとか、そういう話を身近に聞いていたので、被ばくしたら差別されるんだっていう意識が植え付けられていたんですよね」
新型コロナウイルスが流行し始めた頃のことを再び思い出す。コロナ禍を通して「ウイルスと同じくらい怖いのは人間だ」という声を何度も聞いた。
感染した人を誹謗中傷する行為があちこちで話題になったが、そうした行為と原発事故被害にあった人を中傷する行為は同質だ。災いが起き、不安や恐怖に取り憑かれたとき、渦中に巻き込まれてしまった人を叩く心理はどこからくるのだろう。自分が安全地帯にいることを確認して安心したいのだとしたら、その「安心」とは何なのだろうか。
ちひろさんの懸念は、被ばくに対する差別だけではない。
高校時代、白血病になった福島県内の高校生がそのことをTwitterに書き込んだところ「バズってしまった」という話を聞いたことがあった。線量計を持った大勢の大人たちがその学校に乗り込んで、あたり一面に“危険区域”という貼り紙を貼り、それをYouTubeにアップしたことで大騒ぎになったらしいのだ。被害を広く伝えるという大義名分があったのだとしても、それによって平穏な暮らしを掻き乱されるのはつらい。
「病気がバレたら騒がれる、という事態がある以上、言ったら危険だなって……。差別も怖いし、良かれと思って騒がれるのも怖い。がんのことは誰にも言わないようにしようって決めたんです。実際、友だちとの世間話のなかで『誰かの知り合いが甲状腺がんになった』という話題が出ても、それ以上は触れないようにしようっていう空気が流れていましたね。みんな気をつかって、そこには踏み込まないようにしていたような気がします」
ただ、ちひろさんは人に恵まれていた。甲状腺がんのことを打ち明けたのはわずかな人たちだが、差別的なことを言われたことは一切なく、誰もが心を寄せてくれたという。
「一度だけすごく傷ついたのは、首のところにべつのしこりを見つけたから病院に行ったら、お医者さんに『また見つけてきたの?』って笑われたことですね」
差別という意味あいとはまた異なるが、頼りになるはずだった医師が言い放ったその一言は、今でも忘れられない。
[ライタープロフィール]
棚澤明子
フリーライター。原発や環境、教育、食など、社会課題を主なテーマに執筆。著書は『福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を』『福島のお母さん、いま、希望は見えますか?』『いま、教育どうする?』(弘田陽介氏との共著)(すべて彩流社)ほか。16歳、19歳の男の子の母親。