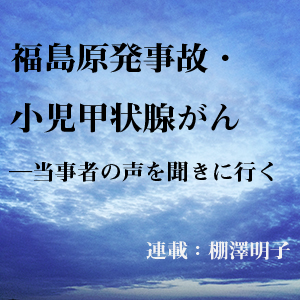第2回 「はじめに」付記 甲状腺がん裁判を理解するために
棚澤 明子
甲状腺がん当事者へのインタビューというこの連載記事をお読みいただく前に、原発事故と甲状腺がんの因果関係にまつわるいくつかのポイントを理解しておいていただければ幸いです。
少し難しいところもあるかもしれませんが、ぜひ、おつきあいください。
1. 原発事故が起きると、なぜ子どもの甲状腺がんが心配されるのでしょう?
原発事故が起きると放射性の「ヨウ素131」が空気中に大量に放出され、人間の甲状腺はこの「ヨウ素131」を取り込んでしまいます。
なぜなら、常日頃、甲状腺ホルモンを合成するために食べもの(ワカメなど)からヨウ素を取り込んでいる甲状腺は、安全なヨウ素と危険な「ヨウ素131」の区別がつかないからです。
「ヨウ素131」を取り込んでしまった結果として生じるのが甲状腺がんです。
新陳代謝を促す甲状腺ホルモンは、子どもの成長に欠かせないもの。子どもの甲状腺は大人以上にヨウ素を取り込む性質があります。だから、原発事故後は大人以上に、子どもの小甲状腺がんが心配されるのです。
チェルノブイリ原発事故後のベラルーシでは、小児甲状腺がんが通常の72.6倍も増加し(*)、国も原発事故の影響であることを認めました。
尚、小児甲状腺がんの原因は「被ばく」「遺伝」「肥満」の3つだと言われています。裁判では、「被告(東電)側が被ばく以外の原因を立証できない限り、原因は被ばくであることが認められるべきだ」と原告たちは主張しています。
*Yuri Demidchik氏資料より
2. 福島県ではいつから甲状腺癌の検査が行われ、どのような結果が出ているのでしょう?
福島県では、2011年6月から事故当時18歳以下だった子どもたちを対象に、「県民健康調査」と称した甲状腺がん検査に着手しました。この検査は一度きり終わるものではなく、1巡目(2011年〜2013年)、2巡目(2014〜2015年)、3巡目(2016年〜2017年)、4巡目(2018年〜2019年)、5巡目(2020〜2021年)と繰り返し行われるものです(25歳時には節目の検診も行っています)。
「はじめに」では、甲状腺がんが見つかった子どもの人数を「338人」お伝えしましたが、2023年3月23日にこの「県民健康調査」の検討委員会が開かれ、新たに6人が甲状腺がんだと診断されたことが公表されました。これまで「県民健康調査」で甲状腺がんだと診断された子どもが302人、がん登録で把握された集計外の子どもが43人、合計すると現在、345人が甲状腺がんに罹患していることになります。
3. 裁判ではどのような点が争点になると思われるのか?
裁判において、被告(東電)は、以下の①〜⑤のような主張をしてくると思われています。それに対して、原告(甲状腺がん当事者)がどのような反論をするのかについて、弁護団の説明を元に筆者がまとめました。
① 被告は「そもそも、年間100ミリシーベルトを超える被ばくをしなければ、甲状腺がんになる可能性はない」と主張するでしょう。
それに対して、原告側は以下のような点での反論を展開する予定です。
・国際放射線防護委員会(ICRP)は「放射線被ばくには“これ以下なら絶対に安全だと言える”というしきい値はない」という「LNTモデル(しきい値なし直線仮説)」を採用しています。
・チェルノブイリ原発事故後の小児甲状腺がんを研究したミコラ・トロンコ氏(ウクライナ内分泌代謝研究センター所長)の論文によると、現地で甲状腺がんに罹った子どもの甲状腺被ばく量は36.2%が50ミリグレイ以下、しかも15.6%は10ミリグレイ以下でした。「甲状腺被ばく線量10ミリグレイ=甲状腺等価線量10ミリシーベルト」なので、100ミリシーベルト以下どころか、10ミリシーベルト以下でも甲状腺がんになり得る、ということがチェルノブイリ原発事故ですでに明らかになっています。

(311子ども甲状腺がん裁判弁護団資料より)
・原発事故が起きた際には、甲状腺を前もって安全なヨウ素で満たして放射性ヨウ素が入り込まないようにするために、18歳以下の子どもたちには「安定ヨウ素剤」を配布する、ということが国際的に決まっています。
世界保健機関(WHO)は、1999年から子どもや妊婦、授乳中の女性の安定ヨウ素剤の服用基準を被ばく線量10ミリシーベルトと定めています。また、国際原子力機関(IAEA)は、2011年にこの服用基準を被ばく線量100ミリシーベルトから50ミリシーベルトに下げました。その背景には、チェルノブイリ原発事故の際、50ミリシーベルト以下の被ばくでも甲状腺がんが増加するという疫学調査の結果があります。
以上のことからも、「100ミリシーベルト以下の被ばくで甲状腺がんになるはがない」という主張には、説得力がないと言えるでしょう。
② 被告側は「そもそも、福島の子どもたちの被ばく量は少ないはず。なぜなら、甲状腺直接測定で正味被ばく線量が0.2マイクロシーベルトを超えた子どもはいませんでしたよね? ほとんどがゼロでしたよね?」という主張をしてくるでしょう。
それに対して原告側は次のように反論する予定です。
・甲状腺直接測定は3月24日〜20日にわずか1080人を対象に実施されただけです。それだけのデータで何事かを確定することはできません。(チェルノブイリ事故後のウクライナでは35万人を対象に甲状腺直接測定が実施されました)
・3月28日のいわき市の測定所でミスがあったことが後に判明しています。ここでは、バックグラウンドの線量として「場」の線量を引かなければならないところ、誤って「着衣」の線量を引き、その結果として甲状腺の被ばく量が極端に低い数値となっています。
③ 被告側は、「2020年にUNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)は『日本人はワカメなどヨウ素を多く含む海藻を日常的に食べる食習慣があるから、甲状腺がヨウ素で満たされていたはずだ。だから、原発事故で放射性ヨウ素を取り入れる危険性は低い』として、甲状腺吸収線量を2013年と比較して1/2に評価し直しました。そもそも、日本人は原発事故が起きても甲状腺がんに罹りにくいのです」という主張をするでしょう。
それに対して、原告側は次のように反論します。
・現代において、毎食ワカメの味噌汁を食べるような食習慣をもっている子どもは少数派でしょう。尿中のヨウ素を測る調査から、2019年時点における日本の小児(学童)のヨウ素摂取量は標準範囲内であり、174カ国中23位と、決して過剰ではないことが証明されています(Global scorecard of iodine nutrition in 2019 in the general population based on schoolage children(SAC) 2019年学齢期の子どもを基準とした一般集団におけるヨウ素栄養のグローバルスコアカード)より)
④ 被告側は、「原発事故後、福島県内で甲状腺がんの発生率には地域差が出ていません。放射能汚染ががんの原因なのであれば、避難区域での発生率が一番高いのではないでしょうか?」という主張をするでしょう。
それに対して、原告側は次のように反論します。
・1巡目の結果では確かに地域差は出ていません(避難区域等33.5%、中通り37.2%、浜通り43.0%、会津地方32.6%)。しかし、2巡目では明らかに地域差が出ています(避難区域等49.2%、中通り25.5%、浜通り19.6%、会津地方15.5%)
明らかな地域差が出たとたん、評価部会は地域ごとの解析を中止したので、その後、同じ条件での分析が不可能になっています。
⑤ 被告側は「チェルノブイリでの甲状腺がんを参考にしているようですが、患者の年齢層がチェルノブイリに比べて圧倒的に高いですよね?」と主張すると思われます。
それに対して原告は次のように反論する予定です。
・チェルノブイリで小児甲状腺がんが乳幼児に多発した原因は、汚染されたミルクによる内部被ばくだと考えられています。日本では粉ミルクは全国的に流通する商品なので、乳幼児が必ずしも地元で生産されたミルクを飲むというわけではありません。むしろ、事故直後に防護されなかった小、中、高校生に多発したと考えるのが自然ではないでしょうか? 不運なことに、原発事故は多くの高校の合格発表とタイミングが重なりました。線量が高い時期に、屋外で抱き合って合格を喜ぶ受験生の姿も報道されています。
こうしたことから、患者の年齢層についてチェルノブイリとの単純比較には意味がないと思われます。
以上のような争点を理解した上で、裁判を見守っていきたいと思います。
次回から連載する甲状腺がん当事者のインタビューも、「若者たちががんになってしまってかわいそう」という視点だけでなく、こうした争点について理解した上でお読みいただくことで、より真実に迫れるかと思います。
さらに詳しく知りたいという方は、「311甲状腺がん子ども支援ネットワーク」のホームページなどをご覧いただくことをおすすめします。

[ライタープロフィール]
棚澤明子
フリーライター。原発や環境、教育、食など、社会課題を主なテーマに執筆。著書は『福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を』『福島のお母さん、いま、希望は見えますか?』『いま、教育どうする?』(弘田陽介氏との共著)(すべて彩流社)ほか。16歳、19歳の男の子の母親。